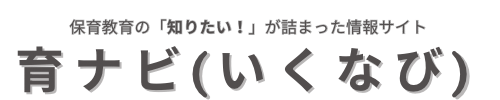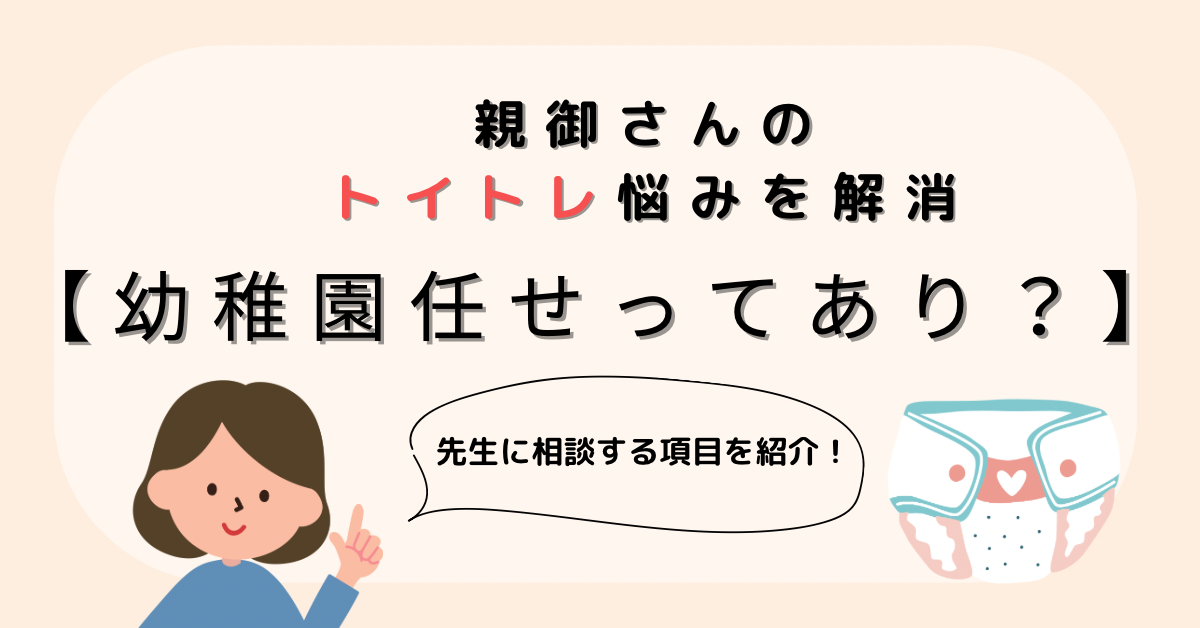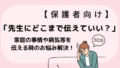こんにちは!はち先生です。
トイレトレーニング通称「トイトレ」ですが、オムツが取れるように家庭でトレーニングをするのが一般的です。しかし、最近は幼稚園に任せていることが良いか悪いか議論が波紋を広げています。
なぜ家庭と幼稚園でトイトレに対する認識が違うかというと・・・
- 幼稚園と保育園の機能の違いが世間一般に知れ渡っていない
- 身近に教えてもらう人がいない(祖父祖母が近くにいない・転勤族で知り合いがいないなど)
- 共働きでトイトレにかける時間が取れない
などが理由として挙げられます。
幼稚園では「トイトレは家庭でするもの」という意見に対して、親御さんの中には、「トイトレの仕方がわからない!」、「仕事も忙しくて家庭ですすめられない!」などの悩みをもっている方もいると思います。両者が別の方向を向いていては嫌悪がつのるばかりで解決にも歩み寄りにもなりません。
💡幼稚園に入園する前に知っておきたいトイトレ情報として、保育園・幼稚園で働いたことのある私がトイトレについて有意義な情報を紹介します!これで、幼稚園準備もバッチリ!先生に聞くこともわかるし、家庭でどんなことを実践すればいいかがわかりますよ。
この記事では、入園までに知りたいトイトレの知識を紹介していきます。
それでは、どうぞ!

この記事はこんな人にオススメです。
- 幼稚園入園前にオムツを外した方がいいか悩んでいる親御さん
- 入園前の準備をしたい親御さん
- 幼稚園で働く先生

トイレトレーニングとは
通称「トイトレ」と呼ばれます。トイレトレーニングとは、オムツを卒業するための練習です。
便器で排泄ができるようになるなど、排泄に関しての自立を目指すトレーニングです。
オムツ外しが遅れてきている!なぜ?
オムツが外れる時期が遅くなった理由として、オムツの性能が良すぎる!ということがあげられます。
今のオムツは、「蒸れない!」「サラサラ!」「動いてもズレない!」など、オムツで快適に過ごせるものばかりです。
オーガニックのオムツが発売されるなど、赤ちゃんのオムツ生活が豊かになるように改良されています。その反面、オムツを外すタイミングは親の見極めに委ねられています。
ここで、私が幼稚園の先生をしていた時の話。未満児クラス(満2歳)で驚いたことがありました。それは、おしっこが出ても水色の線が出ないものがあることと、おしっこが出ていても見た目ではわからないほどの生地の薄さだったことです。こんなに性能がいいオムツを履いていれば子どもも不快感を覚えません。幼稚園は日中の活動がメインですが、たくさん動いても長い時間オムツを履いて過ごせてしまうので、「こまめにオムツ替えをして不快感や清潔感を覚えさせて、トイレに促す」という配慮が難しくなっている現状を知りました。
保育園で働いていた時から4〜5年しか経っていない間にオムツの性能アップによって、オムツが外れる時期が遅くなる理由だと気づきました。
このように、オムツの性能が良くなってきているから、赤ちゃんからのサインがわかりづら苦なり、親の見極めに委ねられているんだと思います。
トイトレ開始の見極め2ステップ
オムツの性能が良くなっていることによって、トイトレは親の見極めが重要と説明しましたが、では、具体的にどのようなステップでお子さんのサインを見ていくか解説します。
ステップ1 始める時期
家庭で始める時の目安の例を説明します。「適齢期」ではないので、お子さんに合ったタイミングで始めましょう。
- 開始は1歳半からが目安です。
- トイトレ開始〜練習〜完了の理想は1歳半〜2歳くらいが目安です。
- 完了は3歳くらいまでが目安です。
ステップ2 サイン
以下の全てにチェックが入ればトイトレ開始ということではありません。1つでも当てはまれば、「そろそろ始めてみようかな」、「トレパン(トレーニングパンツ)買って準備しようかな」というくらいで構えてみましょう。
- おまるやトイレに興味を持っている、座ってみようとする、座っても嫌がらない
- 排泄した時にオムツを気にしたり、気になることを訴える素振りをする、「シーでた」など言葉で表す
- おしっこの間隔が長くなる、2〜3時間ほどオムツが濡れていない時間がある
- オムツやトレパンを持ってきたり、履いたり脱いだりしようとする又はできる
保育園ではいつから始める?
家庭でのトイトレのステップを解説しましたが、では保育のプロが集まる保育園ではどのようにトイレの練習をしているかも覗いてみましょう。
保育園では、0歳児クラスの後半から始めます。月齢で言うと1歳6ヶ月位です。1歳児クラスになると本格的にトイレの練習開始というところです。
保育園ではトイトレという言葉は使いません。園によって呼び方は異なりますが、「トイレの練習」となります。最近は個人差に配慮した保育が定着してきているため、1歳児〜2歳児クラスの間にトイレの練習・オムツが取れるように排泄に関する計画を緩やかに設定している園が多いと思います。
1歳児クラスになると、生活の中で排泄や衣服の着脱が年間の計画に入ってきます。そのため、「排泄」に関しては、保育計画として「オムツが取れるようになる」「トイレで排泄ができるようになる」といったゴールが設定されます。※個人差の配慮があります。
一斉保育にこだわる園やオムツをとる年齢にこだわりがある園などは「1歳児になったら全員がオムツ取れるようにします」と目標を掲げているところもあると思います。そのような園に預けた親御さんは「早くオムツを取ってくるから助かった」と話す人もいます。
「そんな園もあるの!?」と思われる方もいると思いますが、排泄に関して、個別に合わせるか、オムツをとる時期が決まっているかはお子さんのペースや親御さんの意向もあると思うので、気になる方は入園前に聞いてみてください。

私が保育園で働いていた頃の話を少し。排泄をオムツからトイレに移行する時期の0歳児〜1歳児では、子どもの方から不快感を訴えたり、おしっこでパンパンのオムツを触って気にする素振りを見せてくれます。そのサインを読み取って、「うんちがでたね気持ち悪いね」「綺麗にして気持ちよくなろうね」と子どもの気持ちを代弁するように言葉で伝えることも排泄のサポートをする際に欠かせないポイントでした。そうすることで、子どもは自然に排泄に対して意識をするようになります。
保育園のトイレの進め方
保育園では、保育計画などは厚生労働省の「保育所保育指針」に基づきます。
保育所保育指針では、1歳〜3歳が身体の機能の発育・発達に伴い、排泄が可能になる時期とされています。
保育園のトイレの進め方の目安の1つは年齢です。排泄を意識し始める時期・トイレの練習を始める1歳半〜2歳くらいの月齢になったら「トイレに行ってみる?」と促し始めます。必ずその月齢から始めるというのではなく、個々の様子を見ながらです。
集団生活であるため、普段からお兄さんお姉さんのトイレに行く姿をみていると「自分も真似したい」という思いが生まれます。真似をしてトイレに行こうとしている姿を見た時は、午睡明けなどにトイレに行って、便器に座る体験をします。そこでおしっこが出なくてもOKです。「便器に座れた」とうことが第一ステップで、まずはトイレという場所や便器に慣れます。男の子も座ってします。立っておしっこするのはまだまだ先です。まずは、女の子も男の子も、座れることやおしっこが出る感覚を覚えます。
トイレの進め方の目安の2つ目は間隔です。
- おしっこを溜められてきているか
- オムツが濡れていない時間が長くなってきているか
- 午睡明けにオムツが濡れていない
などが「そろそろトイレ行ってみようか?「トイレでおしっこできそうだね」というタイミングです。
あくまで目安なので、個人のペースを守ります。トイレの場所が苦手な子、便座に座るのが苦手な子、排泄の感覚が掴めない子ももちろんいます。
排泄やトイレに関して「いやだ」「怖い」というネガティブな感情を持たないように、保育士たちはおしっこが出たら「やったね!でたね!」「スッキリしたね!」「今日は座れたからOK!」と個人を尊重した対応を行います。

幼稚園ではトイトレをしている?
結論、トイトレはしていません。なぜなら、幼稚園は幼児教育を行う場所だからです。
幼稚園の役割はこちら↓
3 幼稚園の役割
幼児期の教育は,大きくは家庭と幼稚園で行われ,両者は連携し,連動して一人一人の育ちを促すことが大切である。幼稚園と家庭とでは,環境や人間関係の有り様に応じてそれぞれの果たすべき役割は異なる。家庭は,愛情としつけを通して幼児の成長の最も基礎となる心の基盤を形成する場である。幼稚園は、これらを基盤にしながら家庭では体験できない社会・文化・自 然などに触れ,教師に支えられながら,幼児期なりの世界の豊かさに出会う場である。
引用:幼稚園教育要領解説|平成 30 年2月文部科学省
幼稚園の特徴はこちら↓
- 3歳児(満4歳から)からの入園。
- 保育園のように、トイレ練習を始める0〜1歳児クラスはない。
- 最近はプレや未満児クラスはあるが、各週の預かりなど各園で異なる。
- 日中の活動時間が4時間ほど。
- お弁当又は給食を食べて帰る。
幼稚園では、就学前教育としての役割もあるため、半日という限られた時間の中でとにかく活動を行います。そのため、幼稚園の先生はトイトレ<活動と、「活動時間」の比重の方が大きいです。
【本題】幼稚園入園前にオムツがとれていた方がいい?
前置きが長くなりましたが、ここで本題の「幼稚園前におむつはとれていた方がいいのか」という話に入っていきます。
ここまでを整理すると
- オムツの性能が良くなってきているので、外すタイミングは親御さんに委ねられている
- 保育園では0歳児〜1歳児クラスでトイレの練習を始める
- 幼稚園では就学前教育の役割があるため活動がメイン
これらを踏まえた結論を次に話します。
【結論】
【結論】園と相談して進める
理由は、近年の子育て世代の変化を幼稚園側も理解しているが、幼児教育という「教育」「活動」という環境であるため、万全なサポートができない。という理由が挙げられます。
そのため、オムツをとる・トイトレをするのは家庭で進めて、補助として幼稚園に協力を求める。という形がベストです。
次に、実際に相談する内容を紹介します。
先生に相談する内容
私が実際に、保護者から受けたトイトレの相談とその回答を紹介するので、参考にしてみてください。
プレ保育や未満児クラス、3歳児入園まもない頃、なかなかトイトレが進まない子を想定します。
親御さんは、このような内容を相談してみてください。
- いつまでにオムツが取れた方がいいか
- 家庭ではどのように進めたらいいか
- バスに乗る時はオムツがいいかパンツがいいか
- 持ち物はあるか(トイトレ用パンツや着替えの補充など)
私がこれに答えるとしたら、
- 目標は夏ごろまでに取れるといいですね。理由は、体も大きくなり運動量も増えるので、蒸れてきたりもしますし、オムツが取れるとより活発に活動できます(プールなどはオムツが取れていることが条件になっている園もあります)
- おしっこの間隔があいてきたり、トイレに興味が出てきたタイミングで座らせてみてください。休日などにパンツで過ごしてみてパンツに慣れる回数を増やしてみてください。
- バスはオムツで、日中は園でパンツに取り替えてみましょう。
- 園でパンツで過ごしてみるので、トイトレ用のパンツ3枚と着替えを多めに準備してください。
このような感じで、園の進み方と家庭で進み方に大きな相違が生まれないように、連携をとります。
親御さんは、トイトレを始める!と決めた時は、あまり力まずお子さんのペースに合わせて促してみてください。ただし、注意があります。必ず、トイトレを開始した・進めていることは園に伝えましょう。そして、進歩状況を共有しましょう。家庭と園で対応が違うとお子さんが混乱してしまいます。園と情報共有しながら、同じペースで進めていくことをオススメします。

ここで一言アドバイス!
【 家庭での言葉がけと関わり方 】
オムツが濡れていたら、「気持ち悪いね」などの言葉がけとともにオムツ替えをします。その後、「さっぱりしたね」などの言葉がけをすることで、清潔に対する心地よさの感覚が育ちます。このように毎日、毎回繰り返すことは、衣服の着脱時も同じです。清潔である状態を言葉に出して伝えてあげることで、清潔に関わる行為の意味を感じ取っていきます。

まとめ
幼稚園入園前に知っておきたいオムツ事情と園とのやりとりは↓
- トイトレやオムツが取れていないことなどは園と相談して進めていこう
- 幼稚園は幼児教育や活動がメイン
- オムツの性能が高いため、不快感を覚えにくいので親の見極めが重要
- トイトレの目安は1〜3歳くらい
社会の変化によって、幼稚園でも働く親御さんのためにトイトレに協力的な園もあると思います。しかし、園の保育方針や日中の活動量によっては、お子様のペースに合わず、トイレが嫌になったり疲れたりしてしまう可能性もあります。そのため、園選びも重要ですが、お子様のペースに合わせたトイトレを行えることが最も重要だと考えます。
ぜひこの記事を、トイトレ・幼稚園の入園準備の参考にしてみてください。