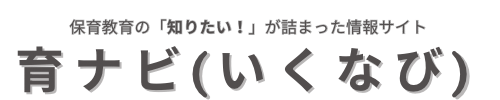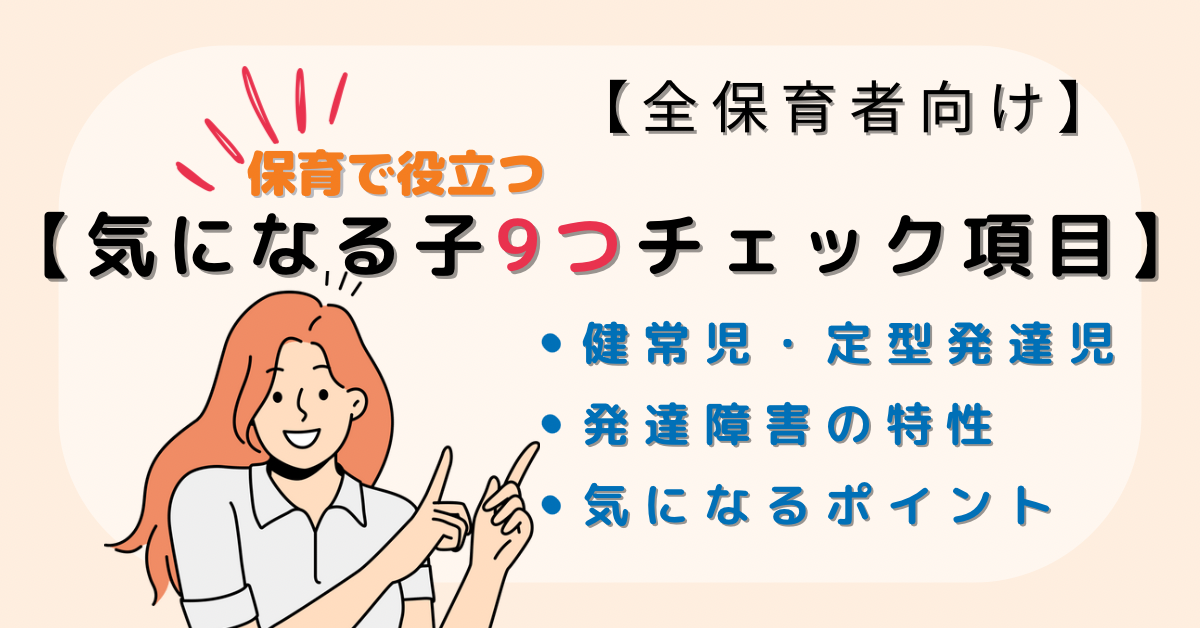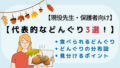こんにちは!はち先生です。
近年、「多様性」という言葉は、教育や保育の指針にも含まれる重要なキーワードになりました。保育現場でも「言葉が遅い」「集団に馴染めない」「多動傾向がある」「こだわりが強い」など、発達障害の診断の有無に関わらず「多様性」という言葉に括られるようになりました。そしていつからかそのような子どもたちのことを「気になる子」と呼ぶようになりました。
今では保育用語となっている「気になる子」という表現ですが、果たして気になる子とはどのような子を指すのでしょうか?
今回は、近年保育現場で増えている「気になる子」について、元保育士・幼稚園教諭の私が保育で役立つ「チェック項目」を紹介します!
今更聞けない「発達障害」についても解説していきますよ!「定型発達」「神経発達症」「スペクトラム」全て現代の保育者の必須単語です。
この記事を読めば、日々の記録も取りやすくなりますし、保育時に目を配っておく必要がある子どもの把握にも役立ちます。
それではどうぞ!

この記事はこんな人にオススメです!
- 保育士
- 幼稚園教諭
- 保育教諭
- 保育補助

定型発達児ってなに?
定型発達は「ていけいはったつ」と読みます。英語では、「Typical Development」略して「TD」と表されることがあり、学術論文や医療機関で使われることが多いです。
これに該当する児童は、発達障害のない子どものことです。同じ意味で「健常児」ということがあります。昔の保育現場では、障がいのない子どものことを「健常児(けんじょうじ)」と読んでいたため、「定型発達児」はまだ馴染みが浅い呼び方だと思います。
保育現場では、障害のない子どものことを「定型発達児」や「健常児」と呼ぶことはまずありません。発達障害についての研修等で講義する先生が使う場面に遭遇するくらいです。
しかし、聞きなれない言葉ですが保育者・教育者の知識として知っておく必要があるため、障害のない子ども=定型発達児と覚えておきましょう。
反対に、「健常児」は現代で使う人も少なくなっているため、日常では使わないほうが良いでしょう。
定型発達児と健常児
現代と昔では保育・教育現場で使われる「障がいのない子」「障がいのある子」の表現が異なります。
- 昔 健常児↔️障害児
- 現代 定型発達↔️非定型発達(神経発達症)
神経発達症
ここでまた新しい名前が現れましたね。「神経発達症」です。「発達障害」の医学的な名称だと思っていただければ良いです。
保育・教育現場では障がいのある子どものことを「神経発達症」と表したり記載する場面は少なく、「発達障害」として表すことがほとんどです。
私も実際に使ったことはありません。なぜなら↓
- 保育園・幼稚園に在籍する園児は、年齢的に神経発達症(発達障害)の診断を受けることが少ない
- 保育者等は医者ではないため、独断で発達に関しての判断をしてはいけない
- 成長・発達には個人差があり、就学前の子どもは特にその差が大きい
- もし書類に記載する場面がある場合は、障がいの正式名称を書く
- 成長・発達の個人差の観点から、神経発達症(発達障害)の傾向がある子どもは「気になる子」と表す
このような理由で、現場ではあまり使われないと思います。
「障害」という言葉も「障がい」と表すようになり、児童記録等でも定着した言葉になっていますね。

「障がい」の「がい」はなぜひらがな?
「障害」の「害」の字は、元々「礙」や「碍」の字が当用漢字の制限を受けて使用できないため、代わりに使用されるようになったものでした。 「障害」をひらがな表記で「障がい」や「しょうがい」にすることによって、否定的・マイナスイメージを和らげようと行政の動きがあり「障がい」「しょうがい」と表すようになりました。
「育ナビ」でもわかりやすいように「発達障害」の言葉を使って、さらに追求していきます。
現在の発達障害の種類は?
平成25年のアメリカの精神医学会で発達障害に関わる診断名が変更後、日本では発達障害を大きく3つのタイプに分類しています。
- 広汎性発達障害(自閉症・アスペルガー症候群)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
日本では、上記の呼び名で発達障害を分けています。「育ナビ」でも上記の名称を使います。
参考:独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所
保育本などでは「自閉スペクトラム症」「注意欠如・多動症」と名称が違うものを見ると思いますが、意味合いは同じです。アメリカの精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM–5)」での呼び名を使っているということだけです。
アメリカの精神医学会が刊行している、精神障害の診断と統計マニュアル「DSM-IV」において、広汎性発達障害は診断名としてではなく、分類上の概念として記載されていました。
広汎性発達障害に分類される障害の診断名の一つとして、自閉症が位置づけられていましたが、2013年に出版された最新のDSM-5からは、広汎性発達障害という概念はなくなり、自閉スペクトラム症にまとめられました。
自閉スペクトラム症と広汎性発達障害は、自閉スペクトラム症は診断名、広汎性発達障害はDSM-IVまで用いられていた症状や状態像を示す概念という意味で違いがあるものの、ほとんど同じ意味をもっているといえます。
引用:株式会社 LITALICOライフ(LITALICO LIFE lnc.)

ちなみに、自閉スペクトラム症(ASD)のスペクトラムの意味は「連続性」です。
1 広汎性発達障害
広汎性発達障害には2つの障害が含まれます。「自閉症」と「アスペルガー症候群」です。
⚪︎自閉症の主な特性
- 言葉の発達の遅れ
- コミュニケーションの障害
- 対人関係・社会性の障害
- パターン化した行動、こだわり
⚪︎アスペルガー症候群の特性
- 基本的に、言葉の発達の遅れはない
- コミュニケーションの障害
- 対人関係・社会性の障害
- パターン化した行動、興味・関心のこだわり
- 不器用(言語発達に比べて)
2 注意欠陥多動性障害(ADHD)
主な特性
- 不注意(集中できない)
- 多動・多弁(じっとしていられない)
- 衝動的に行動する(考えるより先に動く)
3 学習障害(LD)
主な特性
- 「読む」「書く」「計算する」等の能力が、全体的な知的発達に比べて極端に苦手
気になる子
「気になる子」の変遷
1960年代は、「問題児」という言葉が集団保育の枠組みの中からはみ出す子どもの総称でした。障害児を含む多義的・広義の用語として使われていたそうです。
1974年に保育所や幼稚園における障害児保育が制度化される中で、保育者が集団保育の中で難しさを感じる子どもたちの中から障害児が区別され、障害児保育に関する研究が進められた結果、障害児以外の子どもの問題が「気になる子」として取り上げられるようになったそうです。
2000年前後から障害のある子どもよりも障害とは判定されていない子どもの保育についての研究を行う中で、保育者から「実は他にも『気になる 子』がいるのです」と質問を受けるようになったことが、「 『気になる』子どもの出現」の始まりだそうです。
「気になる子」という言葉は、学術的な言葉ではなく、保育現場の「障害児」等の研究をしていくの中で現場の保育者から生まれた言葉だったのですね。
気になる子ってどんな子?
皆さんはどんな「子どもが気になる子」として見ていますか?保育者それぞれの価値観や保育観が含まれるのと、「気になる子」の明確な定義がないため、それぞれの先生の中でのチェック項目が異なると思います。
『「気になる子」の変遷』でも話したように、発達障害以外の子どもの問題も「気になる」に含まれると、大きく3つのチェック項目に分けられると考えます。
- 発達障害の診断は出ていないが疑いがある言動が見られる
- 家庭環境の影響で問題と見られる姿が見られる
- その他(成長発達の個人差・発達障害の特性・園への慣れ具合)
この3つの中から、保育者が特に注目するであろう「1発達障害の診断は出ていないが疑いがある言動が見られる」を元に、元保育士・幼稚園教諭の私が0〜5歳児までの「気になるチェック項目」をあげます。
- 集団行動ができない(拒否反応が強い)
- こだわりが強い(他者の意見を聞き入れられない)
- 情緒が不安定(急に怒る・怒りを抑えられない)
- 言葉の遅れ(発達段階と比較すると遅い)
- 他児とコミュニケーションが取れない(無関心・心無い言葉を平気で発言する)
- 注意散漫で怪我をしやすい(周囲を見れていない・注意力がない)
- 他児へ危害を加える(噛みつき・暴力等・何度注意しても言葉より行動が先になる)
- 衝動的な行動が多い(立ち歩き・落ち着きがない・他児とのトラブルが多い)
- 気になる行動が多い(くるくる回る・目線が合わない・爪先立ちが多い・クレーン現象)
「発達障害の特性に該当する」項目が多いですが、私は「他児に危害を加える」「自身を危険にさらす」行動もチェック項目として見ています。
「気になる子」は大体2つ以上の「気になるポイント」を持っていることが多いです。例えば、「集団行動への拒絶反応➕衝動的な行動が多い➕立ち歩くことが多い(いわゆる座れない)」などです。
それ以外は、発達の個人差として「様子見」としています。
その他、不潔さが目立つ・持ち物を持ってこない(ネグレクトの疑い)、言動が乱暴なども「気になるポイント」ではありますが、それらは家庭環境の問題も影響している場合もあります。虐待の疑いや家庭環境の問題は慎重に行わなければいけないため、主任や園長と連携をとって対応しましょう。
チェック項目にあげたような発達障害の疑いのある行動に関しては、クラスの先生にしか気付けないものが多いので、その子のためにも保育環境を変えたり、関わりを変えたりして対応してあげましょう。もちろん、主任や園長への報告も必須です。
その子が生活しずらさを感じているのであれば、できるだけ取り除いてあげて、過ごしやすい環境を作ってあげたいものです。
「気になる子の見極め方」「気になるチェック項目」を知りたいという先生は参考にしてください。
日々の記録も取りやすくなりますし、保育時に目を配っておく必要がある子どもの把握にも役立ちます。

まとめ
保育で役立つ気になるポイントを紹介まとめ
- 障がいのない子どものことは「定型発達児」と呼ぶ
- 発達障害は「神経発達症」と呼ばれ、発達障害の呼び方が変わった
- 発達障害は大きく3つの分類に分けられる
- 「気になる子」は保育者が作った言葉
- 「チェック項目」は、発達障害の特性が見えるかどうか
- 他児に危害を加えたり自身を危険にさらす行動をする子どもは注意が必要
- それ以外は、個人差・保育者との関わりを通して様子見
- 虐待・家庭環境の問題が影響してそうな時は、慎重に対応する
今回は、私の「気になるポイント」の紹介でしたが、皆さんの「気になるポイント」も知りたいです!
教えてくださいね!
参考文献:「保育者養成の観点から見た「気になる子」に関する研究の展望」 中村 涼 安田学術研究論集 52,77-84 2023.