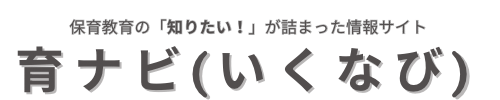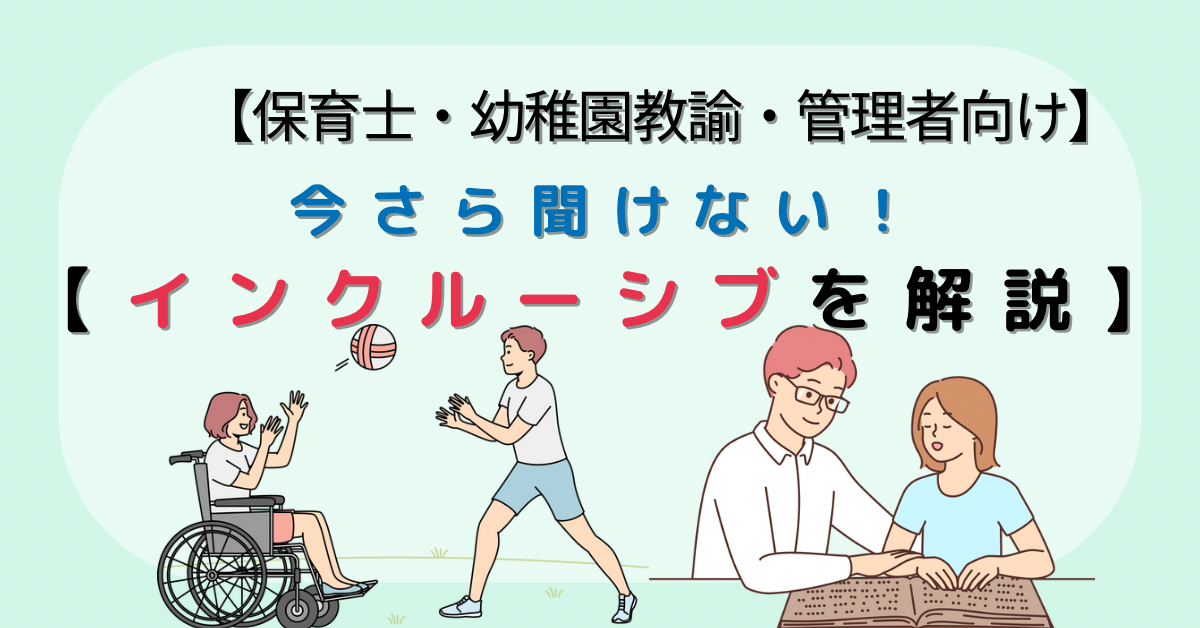こんにちは!はち先生です。
今回は、先生の「知りたい!」の中から「インクルーシブ」について解説します。
発達に障がいがある子やグレーゾーンの子、診断は出ていないけど「気になる子」、医療的ケア児の対応は、園としても保育者としても常に課題として挙げられる話題です。
その他、家庭環境や多国籍、LGBTQなど多様な課題を理解し、対応するスキルを保育者は求められています。
最近は、保育現場でも「インクルーシブ」という言葉を耳にしますが、「よくわからない」という声が多いと思います。わからないのは当たり前。多様性の尊重を言われてきたのは最近なので、まだ現場に定着していないのが現状だと思います。
今知らないとまずい!「インクルーシブ」について、『育ナビ』で一緒に学びましょう!これであなたも保育教育スキルがワンアップします!
それでは、どうぞ!

この記事はこんな人におすすめです!
- 保育士
- 幼稚園教諭
- 保育補助
- 管理職・園長先生

「インクルーシブ」を知ろう
「インクルーシブ(inclusive)」は、「包摂(ほうせつ)的な」「包括的な」「すべてを包み込む」を意味します。
「包括的」とは、あらゆる要素を一つの大きなまとまりとして扱うことです。対義語は、「個別的」です。
インクルーシブ教育とは
「インクルーシブ教育」とは、「障がいのある者とない者が共に学ぶ仕組み」のことです。
インクルーシブ教育の始まり
昭和46年〜50年に、日本においてノーマライゼーション理念が取り入れられ特別支援教育が成立しました。その時期に、世界では既に新たな理念であるインクルーシブ理念が提唱され始めていました。
平成 18 年(2006 年)には、国際連合において「障害のある人たちの権利に関する条約」が提唱され、共生社会の形成、社会における多様性の理解を目指した理念が確立したという背景があります。
文部科学省では、2016年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する条約」が施行され、障害者権利条約第24条「教育」の条文に「障害のある者とない者が共に学ぶ仕組みをつくること」が示されています。
文部科学省
文部科学省では、インクルーシブ教育システムの構築をこのように捉えられています。
まずは、共生社会について↓
「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)概要|文部科学省
このように、障がいがある人も積極的に社会と関わりを持てるようにしよう、共に支え合える社会にしようというのが「共生社会」です。
この「共生社会」を作るためのステップでは、↓
- 共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。
- インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。
インクルーシブ教育システムの構築のための基本的な方向性をまとめると次の通りです。
障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)概要|文部科学省
つまり、私たち保育者が関係していること・現場で行うことは、障がいのある子ない子が同じ場で共に生活し学べるように、多様で柔軟な環境を整えることです。
インクルーシブな支援とは
これまでの「インクルーシブ教育」は、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校での指導や支援のことでした。
「インクルーシブな支援」これこそが、保育者が現場で行うことです。
それは、「どんな子どもにも支援ニーズがあるとみて、一人ひとりの個の育ちや主体性を大切にする支援」のことです。
合理的配慮
インクルーシブ教育と合わせて知っておきたい言葉は「合理的配慮」です。
合理的配慮とは、インクルーシブ教育を構築するために、「学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」です。
例えば、子どもの教育ニーズに的確に対応するための変更・調整の検討を行うことです。↓
- 学習内容の変更や調整
- 教材の配慮
- 学習機会や体験の確保
- 心理・健康面の配慮
- 専門性のある指導体制の設備
- 環境のバリアフリー化やユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業や教室の改善
事例紹介
「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」より、幼稚園での事例を2つ紹介します。
これによって、より具体的にイメージしやすくなります。
「自閉的傾向のある幼児に対する外部専門家と連携した合理的配慮」
「自閉的傾向のある幼児に対する外部専門家と連携した合理的配慮の事例」
インクルーシブ教育システム構築支援データベース|国立特別支援教育総合研究所
本事例は、自閉的傾向(診断は無し)のあるA児(5歳児、3年保育)の事例である。3歳児クラスでは入園当初より一人遊びを好み、自分の好きなことを黙々と取り組み、友達に対して自分から関わる様子は見られず、クラスに馴染めないようであった。4歳児クラスになると、他の幼児に対して自分から関わろうとする姿は見られなかったが、保育者がA児の好きな絵本や恐竜の話をすると、時々笑顔で答える姿も見られた。しかしながら、周りを気にせず自分のペースで好きなことに取り組む一方で、何事においても周りから遅れがちであった。そこで支援の重点を「姿勢の保持や意欲的に身体を動かして遊べるように運動機能を高めていく」「他の幼児と一緒に関わることの楽しさを知り、自ら関わろうとする」として具体的な合理的配慮を行った。姿勢を保持することが困難であった為、這い這い競争やトランポリン、雑巾掛けやサーキット遊び等を自由遊びの中で取り入れるようにした。また、トランプやカルタ、すごろく等ルールのある遊びを通して友達と自然と関わるように配慮した。
「気持ちの切替えが苦手な幼児に対して、関係諸機関が連携し、視覚的な支援等を行うことで幼児が落ち着いてきた事例」
「気持ちの切替えが苦手な幼児に対して、関係諸機関が連携し、視覚的な支援等を行うことで幼児が落ち着いてきた事例」
A児は、B幼稚園の4歳児学級に在籍する幼児である。本件は、A児が、B幼稚園のあるC市立総合教育センターの相談を活用し、特別支援教育担当教員と学級担任の連携のもと支援を受け、園生活を送っている事例である。
A児は、幼稚園入園に当たり、保護者から、気持ちの切替えや感情のコントロールが難しく、個別の支援が必要である旨の申し出があったため、C市教育支援委員会での検討を経て支援に至っている。
入園当初は、自分の思いが通らないと他の園児や教員をたたいたり、物を投げたりすることがあった。また、初めて経験することに不安を覚え、行事の前などはなかなか教室に入れないこともあった。
A児の学級担任、特別支援教育担当教員、保護者が、C市立総合教育センターで実施している医療相談を利用し、A児の実態や支援の方法について共通理解をする場を設けた。幼稚園では、特別支援教育担当教員が学級担任と連携して、A児に他の園児の気持ちや場の状況を伝えたり、視覚的な支援を行ったりするなどの合理的配慮を提供することにより、A児が感情をコントロールできる様子がみられるようになってきている。
このように、インクルーシブ教育、インクルーシブな支援を行うためには、その子の特性や障がいについてよく理解すること、関係機関との連携が必要なこと、その子に合った合理的配慮が必要であることがわかります。

まとめ
インクルーシブについてのまとめはこちら↓
- 「インクルーシブ」とは、「包括的な」という意味
- インクルーシブ教育とは、「障がいのある者とない者が共に学ぶ仕組み」
- 保育者が行えることは、障がいのある子ない子が同じ場で共に生活し学べるように、多様で柔軟な環境を整えること。
- 「インクルーシブな支援」は、「どんな子どもにも支援ニーズがあるとみて、一人ひとりの個の育ちや主体性を大切にする支援」のこと
- 事例を参考にして、自園でも取り組んでみよう
インクルーシブ教育は、小中学校で取り組まれています。そのため、就学前の子どもたちにも同様に、インクルーシブな支援が必要となります。多様性に対応し、子どもが伸び伸びと過ごせる環境の提供が私たち保育者ができることでしょう。
この記事を参考に、明日からインクルーシブな支援を現場で取り入れてみてください!保育スキルがワンアップすること間違いなしです!
参考文献↓
障害児教育におけるインクルーシブ教育への
髙橋純一・松﨑博文 : インクルーシブ教育への変遷と課題
変遷と課題