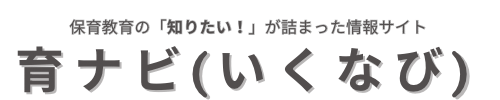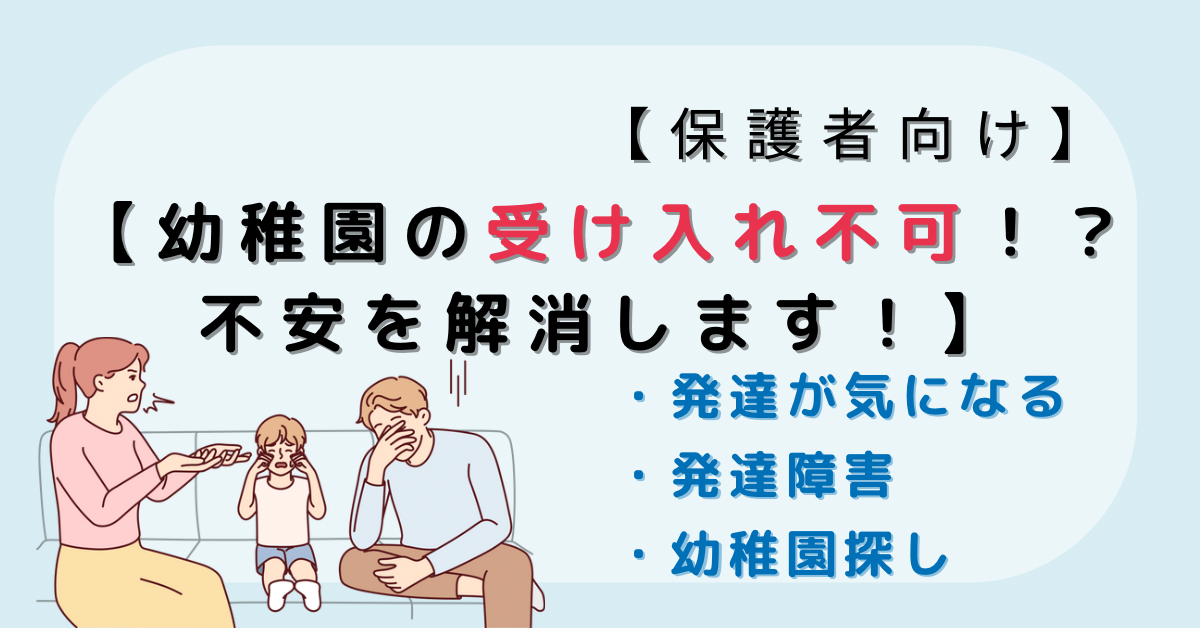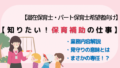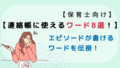こんにちは!はち先生です。
子どもが満3歳になると、そろそろ幼稚園に入園させたいとお考えになる親御さんは多いと思います。小学校入学前に集団生活に慣れてほしい、沢山のお友だちと遊んでほしいなど親の希望は様々ありますよね。就学前の幼児教育には「集団生活に慣れる」「お友だちと一緒に活動する楽しさを知る」「様々な人との関わりで人間関係を学ぶ」など様々な意味があります。
しかし、こんなお悩みはありませんか?
例えば、我が子の発達で今こんなことを感じている↓
- 3歳児検診で発達検査の遅れが見られた
- 児童館や公園など集団で遊ぶ場が苦手だから馴染めるか不安
- 発達障害があるが幼稚園に入学させていいのか知りたい
この記事では、元幼稚園教諭の私が不安を抱えるあなたのために解決策をお伝えします!
それでは、どうぞ!

この記事は、こんな人にオススメです。
- 我が子の発達が気になっている方
- 我が子が集団生活に慣れるか不安な方
- 幼稚園に預けてもいいのか知りたい方
- 発達障害のある我が子の入園を考えている方
※公立・私立での違いやそれぞれの幼稚園で異なることもあるため、参考程度にご覧ください。

ズバリ結論!
結論は、通わせてもOKです。集団生活は苦手かもしれないという理由だけでは入園不可にはなりません。しかし、公立・私立で受け入れの基準があったり、園ごとに受け入れ状況や対応も異なるため確認が必要です。
園を選ぶときに重要なのは、園の特色を知ることです。
私も入園前の親御さんに「少し集団に馴染めないところがあるのですが、幼稚園に入園させても大丈夫でしょうか」と相談されたことがありました。その時の回答は、園の特色とお子様の個性はマッチすることをお伝えました。しかし、親子教室などで1、2回お子様とお会いしただけでは園がどれだけその子のサポートになるかはわからないため、はっきりと大丈夫です。とは言えません。それは、「幼稚園探しの時に子どもの障害や発達に関して相談したところ断られた」ということの幼稚園側の真意でもあると思います。
そのため、幼稚園探しの前に、行うことは、子どもがどのようなことが得意で苦手なのか、幼稚園の生活は合うのかを考えることです。
そうすることで、幼稚園探しも絞りやすくなり、選択も迷わなくなります。
幼稚園とはどんなところ?
我が子が幼稚園でどのように過ごすのか、幼稚園とはどのようなところなのかも入園するかどうかの判断材料にもなります。場合によっては、「幼稚園ではなく保育園の方が我が子には合っていた」ということもあります。就学前の3年という短い期間ですが、子どもにとっては人格形成に関わる大事な3年間でもあります。子どものための最善の選択を一緒に見つけていきましょう。
集団生活のこと
幼稚園に入学させたいと希望される親御さんの多くは「小学校前に集団生活に慣れてほしい」と願い入園を検討します。
しかし、保育園生活などを経験していない子どもには、幼稚園は初めての集団生活の場です。
人間関係の変化からすると、0〜2歳までの親と1対1の関係から、先生や友だち・地域の人など人間関係が広がります。そのため、環境の変化が苦手な子は初めはとても戸惑うかもしれません。好奇心旺盛な子であれば幼稚園で行われる行事や活動に魅力を感じて積極的に参加するでしょう。
集団生活を経験させるメリットはこちらです。↓
- 様々な友達との関わりの中で多様な経験ができる。
- 集団で一つのものを作ったり、役割を分担して一つのことを成し遂げたりする経験を通して、仲間意識が深まる。
- 協力し合うことの楽しさ、責任感や達成感を感じたり、友達にも分かるように自分の思いを主張したり、ときには自分のやりたいことを我慢して譲ったりすることを学ぶ。
- 日々の生活で、友達やもの、場所などに愛着をもち、大切にしようとする意識が生まれる。
- 年齢の異なる関わりで、年下の者への思いやりや責任感を培い、 年上の者の行動への憧れを持ち、自分もやってみようとする意欲が生まれる。
1日の活動のこと
1日の活動時間は約4時間程度です。例えばこんな流れです↓
10時〜11時 朝の会・お集まり・主活動(外遊び・室内遊び)
12時 昼食(給食またはお弁当)
13時 帰りの会・順次帰宅(バス・歩き等)
前後には登園と降園があります。方法はバスや歩き、車での送り迎えがあります。
主な活動内容は、こちらです↓
- 外遊び(担任が計画した活動・園庭で自由遊び・お散歩等)
- 室内遊び(担任が計画した活動・製作活動等)
- 季節に合わせた行事(こどもの日・敬老の日・クリスマス等)
- 園行事(運動会・発表会・芋掘り・餅つき等)
- 保健活動(身体測定・歯科検診等)
- その他、園の独自行事や活動
幼稚園の場合、夏休み(1ヶ月程)や冬休み(1ヶ月程)、春休み(半月程)があるのと、1日の活動時間が4時間程なので、毎日がイベントのようなイメージです。
クラスのこと
子どもの人数は、約15〜30人程度です。規模が大きい園ほどクラスの人数は増えます。近年は、少子化や基準の見直し等の影響で30人クラスは減っているようです。私が働いていた園は小規模でしたので1クラス16〜20人程でした。
先生の人数は、1〜2人。昔は補助の先生もなしで30人を1人で担任していた時代もあったそうですが、今は担任1人と補助の先生が1人の構成がほとんどです。
担任は小学校の先生のようにクラスをまとめ、活動を進める役割があります。そのため、発達が気になる子や発達障害の子の手助けは主に補助の先生が行なっていると考えていいです。担任も、もちろん活動中に手助けを行いますが、全体の安全を見たり活動を進めたりすることが主なので、基本的に発達が気になる子、発達障害の子と一緒に行動するのは補助の先生だとイメージしてください。
様々な特徴を持った幼稚園
幼稚園には大きく分けて公立・私立が存在します。
公立幼稚園の特徴は、
- 国や市区町村などの自治体が運営している
- 教育費関連の負担が少ない傾向にある
- 教育方針に差異がない
- 住まいから近いため通いやすい
- 近隣の情報や小学校情報を入手しやすい
- 地域によっては2年保育のところがある
- 地域の友だちが作りやすく、小学校入学後もそのままの人間関係を築ける
私立幼稚園の特徴は
- 学校法人や社団法人など個人の団体が運営している
- 園によって特色は様々なので、子どもに合った園を見つけやすい
- 教育費関連は負担が大きい傾向にある
- プレ保育や習い事など、多様なニーズに応える特色がある
- 送迎バスがあるところが多いため、自宅から離れていても通うことが可能
- 小学校はバラバラになることが多いため、人間関係が途切れる
- 大学の附属幼稚園がある
- 入園試験や面接がある
公立幼稚園は、文部科学省の幼稚園教育要領に基づき、体系的な教育・保育が行われますが、反対に私立幼稚園は、学校法人などが運営しているため、特色の強いカリキュラムが魅力です。
私立幼稚園の様々な特色
- 教育特化型(読み書き計算などのカリキュラムがある)
- 宗教型(キリスト・カトリックなど)
- 音楽特化型(音大付属、マーチングなど音楽・楽器に触れる時間が多い)
- 自然特化型(裏山や森、自然と関わる時間が多い)
- アート特化型(芸術、感性を伸ばすカリキュラムがある)
- 自由保育型(柔軟に子どもに合わせた保育を行う)
時代の変化に合わせて、こども園として運営していたり、複合的なカリキュラムを実施しているところもあるため、幅広いニーズに対応しています。そのため、発達が気になる子や発達障害児の受け入れ・対応も柔軟になっているところが多いです。
しかし、親の思いと子どもの特性にズレがあると、入園後子どもが馴染めないこともあるため、「発達が気になる」「集団生活大丈夫かな?」と悩む方は、まずは子どもの得意・不得意を知り、楽しんで3年間通える園をオススメします。
入学後、親ができるサポート
無事に入園できたら、幼稚園と協力してサポートしていきましょう。「1日の活動のこと」でも紹介したように、幼稚園は保育園と比べて活動時間が短く、毎日がイベントのような環境です。「ゆっくり支援してもらいたい」という親心もありますが、実際の幼稚園では、個別対応に十分な時間をかけられないのも現状です。そのため、子どものためにも協力体制を組むことが大切です。
小まめに連絡しよう
心配なことがあれば、早めに相談しましょう。
- 友だちのものを取ってしまいトラブルが起きやすい
- 癇癪(かんしゃく)を起こす
- 言葉が遅い
- 気持ちの読み取りが苦手でトラブルが起きやすい
- チック症状が見られる
- 待つことが苦手で一人行動をしてしまう
特に、友だちにケガを負わせてしまう可能性がある行動は伝えておきましょう。そうすることでトラブルが減ります。その他、発達障害の診断が出ている場合は詳細を伝え、通っている病院と同じように支援していけるように担任に伝えましょう。
または、幼稚園生活や行事に関することでこんな「困った!」があります。
- 排泄の自立がしていないためプールに入れない。
- 大きい音に敏感なため、避難訓練の方法や音を聞いてパニックになる。
- 整列すること・順番を待つことに慣れず、運動会の参加が難しい。
- 偏食のため、お弁当に入れられるものが少ない。または食べない。
- 多動傾向があるため、集団から外れてしまう。
行事では、より集団行動が問われる場面が多いため、年間行事を確認しながら先回りして担任に心配なことを伝え、最善の対応をとりましょう。
生活のことは家庭で教えよう
- 箸の持ち方、食具の使い方
- 食事のマナー(食器を持って食べる、食具を使って食べる等)
- 排泄、オムツ
- 衣服の着脱(靴下、下着、ズボン、シャツ、ボタン付け外し、上着等)
- 靴の履き方、脱ぎ方
- 持ち物の管理(ものをしまう、片付ける、確認する)
「そんなことも!?」と思われた方もいると思いますが、家庭で行なっている「いつものこと」を園では一人で行うと想像してください。
教えているけど、時間がかかりそうであれば、その都度進捗状況を伝えて、できないところを手助けしてもらえるようにしましょう。そうすることで、園で困ることも減り自己肯定感を下げる経験も回避することができます。

まとめ
「発達が気になる我が子を幼稚園に通わせてもいい?」のまとめはこちら↓
- 幼稚園に通わせてOK!
- 子どもの得意・不得意を知り、マッチする幼稚園を探す
- 幼稚園での生活や特徴を知る
- 入学後は、幼稚園と協力体制を組む
「幼稚園に入れたら驚くほど成長した!」という声をたくさん聞きます。私が担任していたときも保護者の方からそのような言葉をいただきました。
子どもは、先生や友だちとの関わり、日々の活動や行事などの刺激から驚くほどの成長を見せるため、幼稚園という集団生活の場は成長にもってこいの環境と言えます。
子どもの可能性を潰さないためにできることは、「できない」と決めつけないことです。
そして、一人で頑張らないことです。幼稚園と協力しながら就学前の3年間を楽しみましょう!