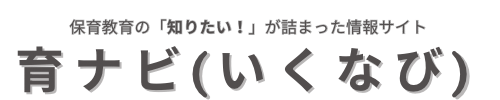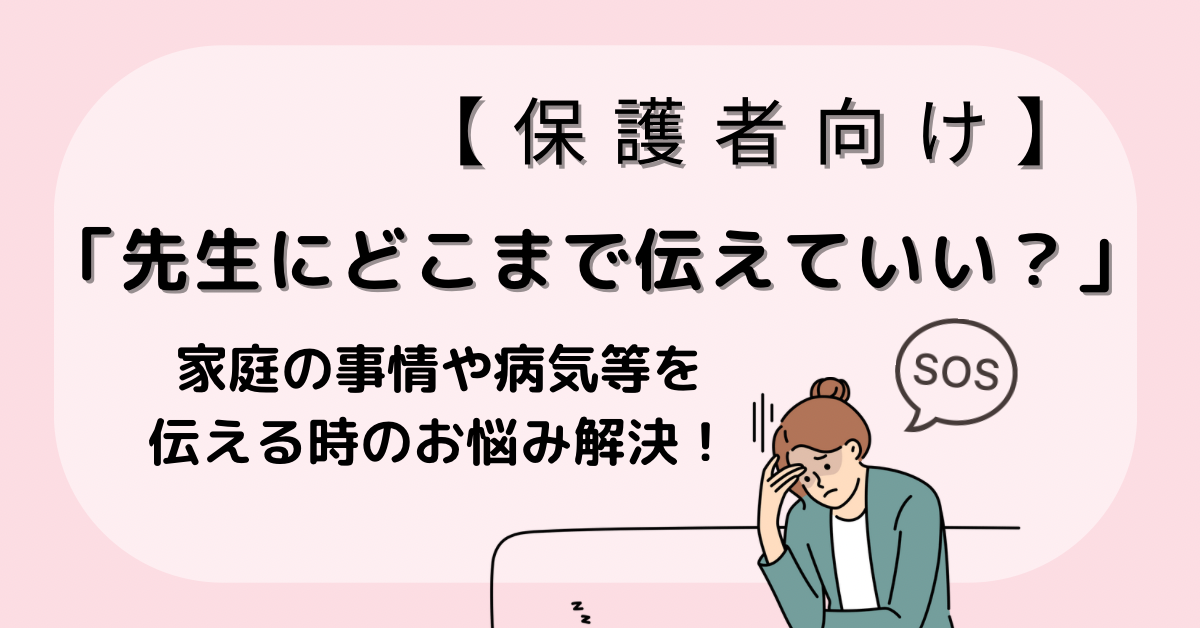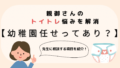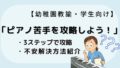こんにちは!はち先生です。
幼稚園で働いていた時に保護者からこんなお悩み相談がありました。

再検査のために入院しなければいけなくなりました。
担任にどこまで伝えていいですか?

家庭の事情で、来週からおばあちゃんが迎えに来ることになりました。
誰にどこまで伝えればいいですか?

自身が病気に。
どこまで詳細に話したらいいですか?今後のお迎えの相談がしたいです。
自分や家族が病気に。入院するためお迎えが行けない。2週間ほど祖母にお願いしています。など、先生に私情をどこまで話していいのか、詳しく話しても担任の先生は困らないだろうか。そのようなお悩みを解決します。
この記事では、「どこまで話す?何を伝えたらいい?」のお悩みに対して具体例を挙げて説明します。
それでは、どうぞ!

この記事はこんな人にオススメです。
- 先生に都合をどこまで伝えたらいいか知りたい人
- 先生はどんな情報が知りたいか知りたい人
- 園への連絡の仕方を知りたい人
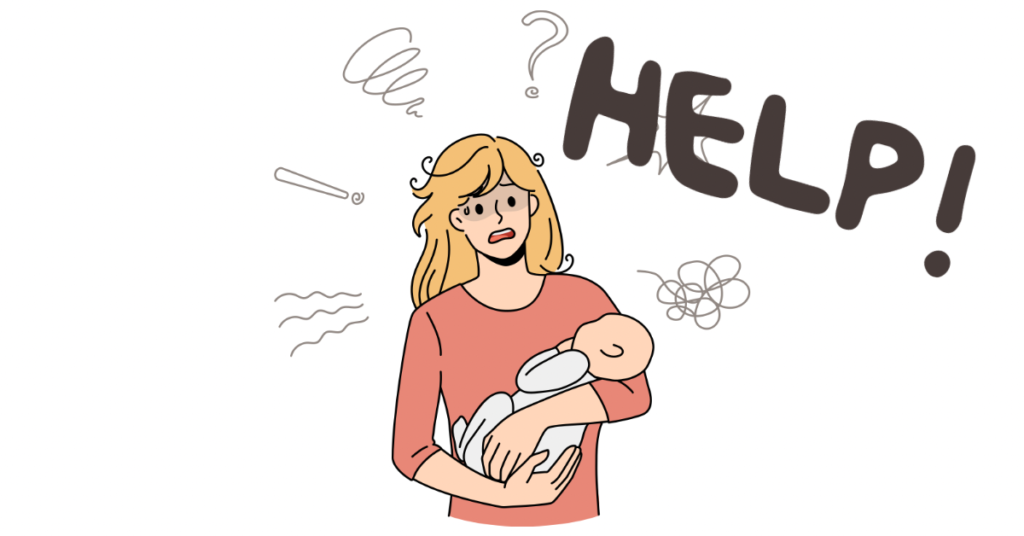
事務的内容と相談事は分けよう!
【結論】担任に全て話してO Kです。なぜなら、私たち保育者は個人情報の取り扱いについて学び、十分に気をつけているからです。園では様々な個人情報を扱います。子どもの名前、生年月日、記録など全て個人情報として慎重に扱い、保管しています。
ただ、注意が必要なのは、正しく情報共有をするということです。
お迎え時に引き取る人が変わることなどは子どもにとっても不安なことです。お子さんが環境の変化によって不安にならないようにするためにも、正しく情報共有をして、先生にもサポートしてもらいましょう。
保護者の方に相談を受ける時に多いのは「出産時」です。安定期が過ぎてから報告を受け、出産時に数週間入院する又は里帰り出産するため、お迎えや引取り者の変更やお弁当等の準備が父親になるため不安、お子さまが精神状態が不安定になるのではいかという相談です。
初めてのことだと、何を話せばいいのかわからないこともありますよね。「正しく情報共有する」ためには、優先順位をつけましょう。それは①事務的な内容②相談事です。
次は、事務的な内容と相談事について解説します。
①事務的な内容とは
例えば、
- お迎え・引取り者の変更「来週から1週間は祖母が迎えにきます」等
- 休みの連絡
- バスに乗るか乗らないか、時間の変更等
- 長期休園「〜月からアメリカに行きます。〜月には帰ってきますが、休みの間の保育料について教えてください。
時間や場所、人、お金などいつもと変更になることは必ず伝えましょう。
伝えなかったら誰が困るか?というイメージだとわかりやすいと思います。
例えば、お迎えの祖母が困る・お迎えを待つ子どもが困る・園からバスの確認連絡が来て自分が困る、状況を把握できない園が困るなど、「これを伝えなかったら誰が困る?」と一度考えてみましょう。
②相談事とは
例えば、
- 子どもの様子(不安定になるんじゃないか等)
- お弁当のこと(いつもと違うお弁当でいいか等)
- 家庭のこと、家族のこと
- ママ友のこと
初めての出来事や急な出来事で動揺したり、急いでいたりすると、事務的な内容と相談事の優先順位が逆になり、「伝えなければいけないことが伝えられていなかった」となることもあります。伝えなければいけないことを伝えなかったために、園から確認の連絡が来たり、普段と違う状況で子どもを困らせてしまうことにもなります。
まず、第一優先は事務的な内容を園に伝えることです。そして不安なことや自分で判断できないことを相談しましょう。
園への伝え方
大抵の園では、保護者の方に寄り添った対応をとってくれます。そのため、事務的な内容を伝える時はこのように伝えてみてください。
- 「○◯日から◯◯日まで休みます。」
- 「○日〜◯日までは送り迎えになりますので、バスには乗りません。」
- 「◯○日から入院するため、その間は祖母が迎えに来ます。名前は◯◯◯◯です。」
- 「この日は通院のため、◯時に引取ります」又は「迎えにいきます」
園でどのように対応してくれるか知りたい時などはこのように質問してみてください。
- 「事情により(家族旅行により等)、◯月◯日から◯月◯日まで、オーストラリアに家族で行きます。その間の保育料について教えてください。」
- 「〜(事情を話し)なのですが、◯日から◯日までのお迎えは叔母の◯◯にお願いしたいと思っています。その際、何か提出するものはありますか?(引取り者で伝えていなかった人が迎えに行く時)
- 「出産のために実家に帰るのですが、その期間だけバス停の変更はできますか?」
- 「この日は、用事があるため早めに迎えにいきたいのですが、午前の活動は何時に終わりますか?」又は「お弁当前に迎えにいきたいのですが、何時頃に食べ始めますか?」
知られたくないことは注意が必要!
子どもに関わることは、担任の先生に連絡し、心配なことがあれば相談しましょう。しかし、いつの間にか噂が広がっていたという事例は少なくありません。
知られたくないこと(病気・家庭の事情等)は、最低限の人と話すことにしましょう。そしてその情報の取り扱いも決めておきましょう。次は、「身近なところで情報が広がる」謎を解明します。
身近なところで情報が広がる
誰も悪くはない状況でも情報は広まってしまうことがあります。気をつけましょう。
情報を広げてしまう可能性がある人
- ママ友
- 家族(夫・祖母・祖父・兄弟等)
- 子ども
1、ママ友は、小さな情報を逃しません。「実は最近体調がすぐれなくて・・・」という小さな情報から噂が広がることも。ママ友の情報網は皆さんご存知の通り、広くそして素早く伝達するので注意が必要です。
2、家族は、お迎えの時などが注意です。なぜなら、「最近、〇〇くんママお休みだけど、どうしたんですか?」と聞かれ、つい話してしまうからです。「つい話してしまう」理由の多くは、“うちのママと目の前にいるママはどういう関係性か知らない“ことです。帰ってきて、「仲が良いと思って話してしまった」と言っていたら「なんで話したのー!」となってしまいます。
3、子どもは、意外と多いです。子どもは断片的に話を聞いて覚えていたり、印象的な言葉や親が繰り返し言っている言葉を覚えていたりします。保育者として実際にヒヤッとするのも、お子さんが家庭の事情を話した時です。子どもはその言葉の意味もわからず話してしまいます。おうちの人のことが大好きだからこそ話したいという気持ちもあります。例えば、「ママはね〜なんだよ」と自慢したり。まだ小さいからと案ずること勿れ。意外に子どもたちは覚えていて、ふとした時に話してしまう時があります。
保育者が「そのことは他の人に言ってはいけいこと」と保護者の方と情報共有している内容であれば、すかさずフォローに入ることができます。そのため、お子さんが言ってしまいそうな時は先に先生に伝えておくことが懸命です。

まとめ
この記事のおさらいです。

- 担任の先生に詳細に伝えてOK
- 優先順位をつけて、①事務的内容②相談事は分けて話そう
- 知られたくない情報の取り扱いには注意が必要
「先生になんて伝えよう」「先生に詳細に伝えて困らないかな?」と迷っている方は、心配ありません。園側も担任の先生も保護者の方、お子様のことを思って柔軟に対応してくれます。日頃のコミュニケーションや情報共有が、円滑な人間関係の構築になりますし、気持ちよい関係でいられる秘訣でもあります。
ぜひ、この記事を参考にして、明日から実践してみてください!