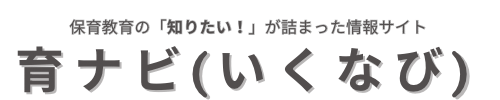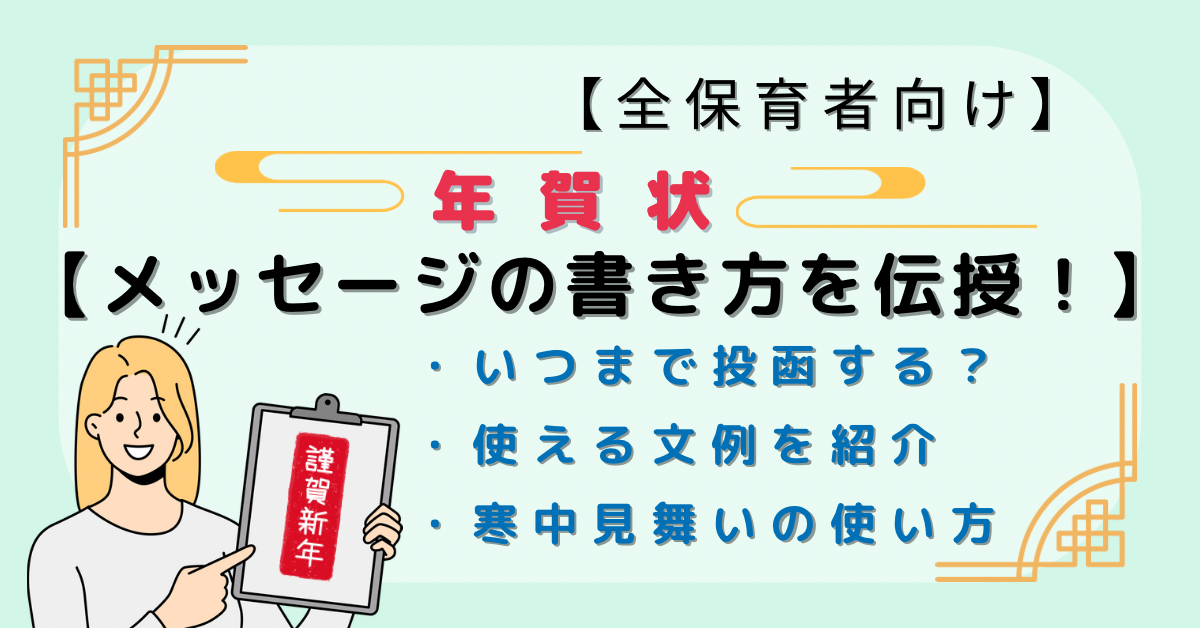こんにちは!はち先生です。
保育園や幼稚園などで「担任は年賀状を手書きする」という決まりがある園もありますよね。
私が以前勤めていた幼稚園でも毎年自分のクラスの子どもたちに年賀状を手書きするという決まりがありました。初めてのことでしたのでどのように書けばいいのかわからず検索した思い出があります。
新人の方は特に、子どもへの年賀状の書き方はわからないですよね。過去の私のように、「年賀状のメッセージは何を書けばいい?」と疑問を持つ先生たちの悩みを解消したいと思います!
これであなたも先生からのメッセージの文面を悩まなくてよくなりますよ!
それでは、どうぞ!

この記事は、こんな人におすすめです。
- 保育士
- 幼稚園教諭
- 保育教諭
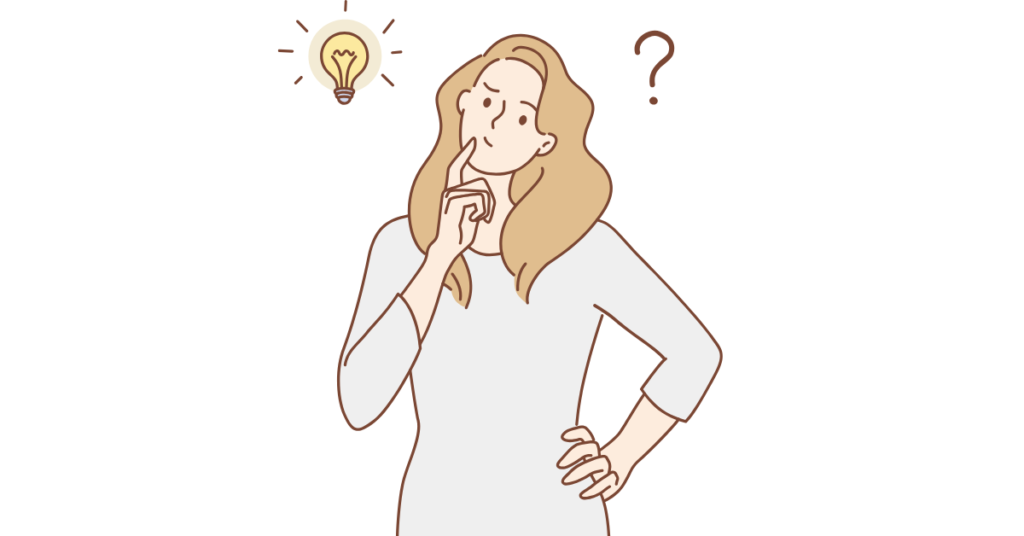
いつまでに投函するのか
元旦に届くようにするには、郵便局の定めている時期までに投函しましょう。例年25日までに投函された年賀状は元旦に届くようになっています。
投函するときは、園でまとめて事務の人が出しているところもあると思いますが、先生個人に任されているところもあると思いますので、いつまでに投函するのかは確認しましょう。
しかし、1点注意があります。「寒中見舞い」は投函時期が異なるため、12月25日まで投函する年賀状と一緒にしてはいけません。
次に寒中見舞いについても解説します。
寒中見舞い(かんちゅうみまい)
寒中見舞いは、このような時に使います。
- 1月7日までに年賀状を出せなかった時の返礼
- 喪中の人
- 年賀状を出しそびれた時
寒中見舞いは、喪中はがきへの返事や喪中にもらった年賀状への返事、喪中と知らずに出した時のお詫びなどにも使用します。
寒中見舞いを出せるのは、1月7日〜2月4日までですが、大半の園は1月の2週目辺りから登園するため、2月4日まで出すことはないと思います。
文例は、こちらです。↓
かんちゅうみまいもうしあげます。
○○ちゃん(さん、くん)、ふゆやすみはたのしんでいますか?
〇〇ちゃんのふゆやすみのおもいでをきくのをたのしみにしているよ!
ようちえん(ほいくえん)でまっているよ!
○○せんせいより
寒中見舞いを出すときは、干支や年賀状をイメージするデザインは使わず、椿や梅、雪など1月に合ったデザインがよいでしょう。子どもが喜びそうな、雪だるまやおもちのイラストが◎
年賀状文例
年賀状の文例は迷いますよね。年賀状は12月25日まで投函(元旦に届くように)することがほとんどなので、未来に向けて書かなくてはなりません。
そのため、保育園や幼稚園から出すときはこんなことを話題に取り込むといいでしょう。
- 今年楽しかったこと
- 来年楽しみたいこと
- 冬休みの思い出
- 子どもが冬休みに楽しみにしていたこと
- 子どものいいところ
5歳児は、自分で文章を読むことができると思いますが、まだ字が読めない子は、親に読み聞かせてもらうということを意識しましょう。
つまり、崩した言葉使いや、先生と子どもしか知らない言葉、失礼と受け取れる言葉などは注意しましょう。親が見ても子どもが見ても嬉しい話題を心がけましょう。
文例はこちら↓
あけましておめでとう!
○○ちゃん(さん、くん)、ふゆやすみはたのしんでいますか?
げんきいっぱいの○○ちゃんだから、ゆきあそびもたのしんでいるかな。
はやくあいたいよ!ようちえん(ほいくえん)であえることをたのしみにしているよ!
○○せんせいより
あけましておめでとう!
○○ちゃん、ふゆやすみはどこかおでかけしたかな?
せんせいも、ふゆやすみをとってもたのしみにしていたから、〇〇ちゃんとたのしかったおもいでをはなしあいたいよ!
たくさんおもいできかせてね!
○○せんせいより
あけましておめでとう!
たのしいふゆやすみをすごしていますか?
せんせいは、はやく○○ちゃんにあいたいです!
たくさんあそんで、たくさんたべて、またげんきにようちえん(ほいくえん)であえることをたのしみにしているよ!
〇〇せんせいより
あけましておめでとう!
ことしもたくさんあそぼうね!
ようちえん(ほいくえん)でまっているよ!
たくさん、ふゆやすみのおもいできかせてね!
〇〇せんせいより
あけましておめでとう!
ことしもげんきにあそぼうね!
ようちえん(ほいくえん)であえることをたのしみにしているよ!
〇〇せんせいより
宛名の書き方
年賀状はの宛先は縦書きです。そのため、番地などを漢数字にするか、数字にするか迷うところです。
園の方針を確認した上で、漢数字で統一するか、数字で統一しましょう。
「教育機関だから」「子どもの見本だから」等の理由で漢数字で統一していることもあるため、意外に注意が必要です。
せっかくの年賀状ですし、漢数字で統一するとかっこいいですね。
子どもの名前
お父さんの名前の横に、お名前と「くん」「ちゃん」「さん」と書きましょう。
漢字の「君」は目下に向かう言葉であったり、「主君」「帝」を指していた時代もあったため、漢字ではなく、ひらがなが◎です。
こんな時どうする?
自身が喪中の場合
先生も「今年は喪中で年賀状出せないんだけど・・・」という方もいらっしゃると思います。
その場合は、まずは園にその旨を確認してください。
しかし、先生の仕事と自身の喪中は切り離して考えることが多いため、子どもに送る年賀状には「あけましておめでとう」と書いてよいでしょう。
私も、自身が喪中の年もありましたが、子どもには関係のないことですし、自分のクラスの子どもだけ「あけましておめでとう」と書かれた年賀状をもらえないということは子どもにとって寂しいため、普段通り年賀状を書きました。
相手が喪中の場合
園で確認はしていると思いますが、冬休みに入るまでに喪中の方のリストアップをしましょう。
先生から子どもへの年賀状なので、問題ありませんとおっしゃる保護者もいると思いますが、家の事情もある方がいると思うので、配慮が必要です。
冬休みに入る前に確認することは、「年内で身内が亡くなったと連絡があった家庭を把握する」ことです。
相手が喪中の場合は、1月7日以降に届くように、「寒中見舞い」を出しましょう。
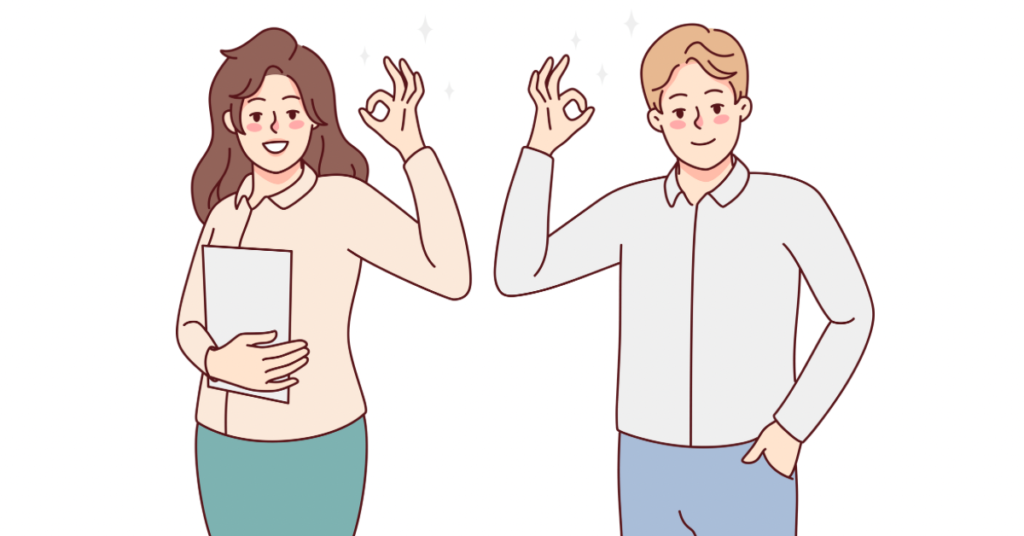
まとめ
年賀状を出すときのまとめはこちら↓
- 元旦に届いて欲しい場合は、12月25日まで投函する
- 喪中の場合は寒中見舞いにする
- 文章は、親と子が一緒に読むことを想定する
- 宛名の子どもの名前は「さん」「くん」「ちゃん」などひらがなで書く
- 喪中の確認をし、時期をずらして寒中見舞いを出す
年賀状を出す機会も減りましたが、手書きの年賀状は子どもが喜んでくれますし、思い出になるものです。
この記事を読み返せば、悩むことなく年賀状を書くことができますよ!
ぜひ、子どもたちが喜ぶ姿を想像しながら年賀状を書いてみてください!