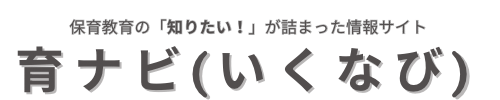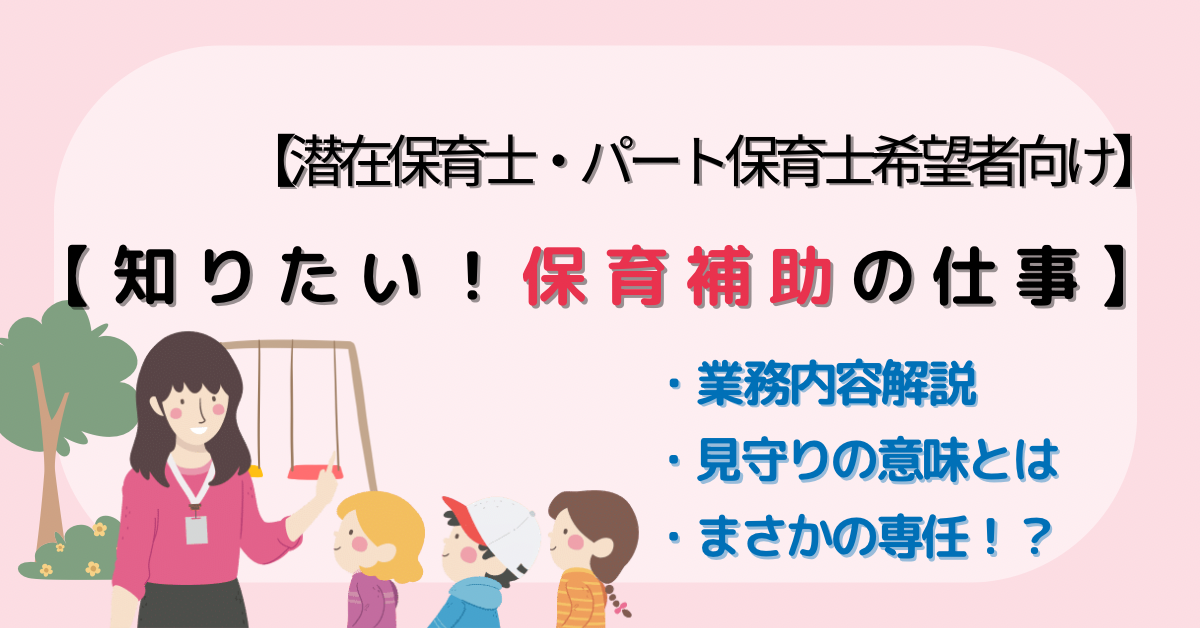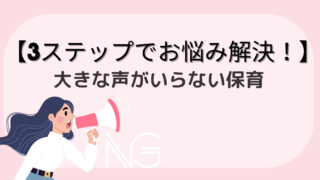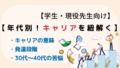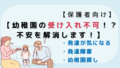こんにちは!はち先生です。
保育補助は、とても魅力があることを知っていますか?担任とは違う視点で子どもの成長を見れたり、持ち帰りの仕事もなければ時間交代できるので子育てと両立することもできちゃうので、お子様がいる方や、ブランクが気になる方は「保育補助」がオススメです!
例えば、今こんなことを思っている方↓
- 子どもを保育園に預けたいので仕事を探したい
- 子育てが落ち着いたので仕事復帰したい
- ブランクがあるのでまずはパートから始めたい
- 幼稚園で働いていたけど、保育園でも働いてみたい
- 保育士資格を取得したので活かしたいけど、まずはパートで慣れたい。
しかし、初めて保育補助をしようと考えている方は「具体的にどんな仕事か」「どのような勤務形態か」気になるところですよね。
この記事では、「仕事復帰したい」「資格を活かして働きたい」と思っているあなたのために保育補助の仕事や時間給などを詳しく解説していきます!
それでは、どうぞ!

この記事はこんな人にオススメです。
- 潜在保育士
- パートタイムで仕事を探している人
- 保育士資格を持ってる人・取得した人
※「保育補助」と言っても一概にパートタイム契約ということではありませんが、この記事では主にパートタイムを想定した内容になります。

仕事内容
保育補助の求人の仕事欄には、「保育業務」「清掃業務」と目にしますが、具体的にどんな仕事になるかお伝えします。
仕事一覧
- 受け入れ・引き渡しの補助
- バスの添乗(バスがある園の場合)
- 子どもの見守り(一緒に遊ぶ)
- その日の活動の用意
- 支援が必要な子の対応
- 食事の配膳・片付け
- ミルク・食事介助(0歳児〜1歳児クラス)
- 着替え・オムツ・トイレ介助
- 寝かしつけ
- 保育室・園内の清掃
1日の流れで見る(デイリープログラムで説明)
8時〜9時 ○受け入れ・見守り(担任が不在時に保護者から連絡を受ける・受け入れた子どもを部屋でみる)
10時 ○活動の補助(活動準備・一緒に遊ぶ・支援が必要な子のサポートに回る)
11時 ○活動の補助(活動準備・一緒に遊ぶ・支援が必要な子のサポートに回る)
12時 ○給食準備・食事介助(0歳児〜2歳児は介助・3歳児以降は見守り)
13時 ○掃除・片付け・寝かしつけ(食事の後片付け・着替えや寝かしつけ・部屋や園内の掃除)
14時 ○制作手伝い・消毒(クラスの制作物または園全体の制作物の手伝い・玩具の消毒など)
15時 ○おやつ準備・おやつ介助(おやつの配膳・0歳児〜2歳児は介助・3歳児以降は見守り)
16時 ○片付け・見守り(おやつの片付けやその日に使ったものを片付ける)
17時 ○引き渡し・見守り(基本的に帰りは担任が保護者に1日の様子を伝えるため、補助は見守り)
※活動の合間には、水分補給の用意やトイレの補助などがあります。
※休憩は12時〜15時の間で取るのが一般的です。(実働6時間を超える場合は労働基準法により休憩があります)
もっと細かく!主にこんなことをしています。
活動の用意・準備
活動の用意・準備とは、担任に変わって一から全て行うということではありません。その日の活動を担任が計画しているので、その時に使う材料等を机などに準備するということです。(外活動の時もあります)
例えば、その日の活動が「クレヨンでお絵かき」だとしたら、補助の行動は、①テーブル・椅子の設置(環境を整える) ②画用紙とクレヨンを人数分用意(使用アイテムの用意) ③子どもが座ったら配布となります。
一概にこの動きになるとは限りませんが、「活動の用意お願いします」と言われたら、このような動きを予想してください。
活動がスムーズに進行するために、補助の役割が存在します。
オムツ替え・トイレ介助
オムツ替えは0歳児〜1歳児クラスの補助になった場合に行います。
また、1歳児クラス以上でもオムツがまだ外れていない子や支援が必要な子(排泄が自立できていない)がいた場合は、オムツ替えの担当になることがあります。
トイレ介助は、トイレの練習をする1歳児〜2歳児クラスの補助になった場合に主に行います。
また、3歳児以上でも、トイレで遊んでしまうことや手洗いがきちんとできているかなどマナーやルールの確認や声がけをするために、補助がトイレについていくこともあります。
支援が必要な子の対応
支援が必要な子とは、発達障がいと診断が出ている子から、診断は出ていないが個別対応が必要な子のサポートです。ほとんどクラスの中ではその子の「専任」という形が多いと思います。園から「専任でお願いします」とは言われなかった場合でも、クラスに支援が必要な子がいた場合は、補助が主に一緒に行動すると考えます。
担任から「○○くんについてください」と言われたら、その時間(活動中や食事中など)はお願いされた子のサポートに徹します。
行事の参加
平日の保育業務とは別に、休日に行われる行事への参加も業務に入ります。パートタイムの場合は時間給なので強制参加ではないと思います。パートタイムの場合、家庭やお子さんがいるため、配慮があるでしょう。
主な休日の行事の種類は↓
- 夏祭り(7〜8月)
- 運動会(9〜10月)
- 秋祭り(10〜11月)
- クリスマス会(12月)
- 発表会(1〜2月)
最近は、保育業界全体で行事の見直しがされているため、負担や休日出勤を少なくしようと各園で工夫されていると思います。
午睡中の業務と注意するポイント
主に、保育室や園内の清掃と園全体の制作物(行事のものや壁面など)やクラスの活動・壁面・行事のモノ作りです。
優先順位は①給食後の保育室の掃除 ②園内の掃除 ③制作の手伝い になると思います。
制作の手伝いでは、「行事のもの」と「クラスのもの」に分かれます。ここでポイントがあります。
- 何で使用するものか確認する「運動会で使うんですか?」「クラスのものですか?」
- 見本の確認をする。「見本はありますか?」
- 使用する色の確認、数の確認「どの色の画用紙を使いますか?」「何個作りますか?」
- クオリティを意識する(線をはみ出していないか、形は揃っているか等)
先生たちには「これお願いします」だけを頼まれる場合がありますが、上記の確認をしないと大変なことになってしまいます。
園でよくある制作事件は、「見本と全然違うものが出来上がり、作り直しになった」「子どもや保護者に配布する(行事で使う)ものなのに出来上がりがバラバラ」ということです。
私が勤めていた園でもよくあり、上司に報告したら、作り直しになりました。
これはどの園でもあるあるです。指示を出した側にも責任はありますが、頼まれた側は完成品と同じように作らなければいけません。なぜなら、「プレゼントするもの」であれば、それなりのクオリティが求められるからです。それなら、市販のものでいいじゃないか!と意見がありそうですが、経済的な理由や手作りの温かみを届けたいなどの理由があります。
また、お願いした側の先生の思いも汲み取ることが大切です。適当に選んだ見本を渡した訳ではありません。その行事に合ったもの・もらったら嬉しいデザインを時間をかけて考えています。
誰でも、自分が思いを込めて作ったものを全く別のものに変わっていたら悲しいですよね。業務をお願いされた側はそのつもりはなくても、それぞれの価値観があるため、完成系が全く違うものになることが多々あります。
作り直しになっては、時間のロスですし、次に仕事を任せてもらえなくなってしまい、人間関係にも影響します。
間違いないのは、「見本通りに作る」です。パーツがなければ確認する、色が分からなければ確認する。最初にこのように確認していれば、その園の制作クオリティもわかってくるので、いちいち確認しなくても良くなります。細かいですが、制作はその人の技量や価値観が反映されやすいものなので、確認をしましょう。
勘違いしないために!「見守り」の注意点
担任の先生は「子ども見ていてください!」と言ってその場を離れることがあります。
「子ども見ていてください!」は仕事一覧の「子どもの見守り」業務に当たります。
「子どもの見守りをお願いします」と言われたら、保育業界では「一緒に遊びながら、子どもたちから目を離さず、危険を察知しながら」という意味になります。
担任がその場を離れたということは、「その場を任された」という意味になり、担任に代わって子ども達の安全に目を配らなければいけません。
「担任が離れなければいいじゃないか」と保育補助さんからツッコミがありそうですが、理想は、その通りです。しかし、子どもに合わせて柔軟に保育を進めていけなければいけないし、突然のケンカ対応や発熱対応、怪我や嘔吐処理、支援が必要な子どもの対応、上司からの業務連絡、保護者対応などが同時に起こりうる環境なので、担任1人では全て対応することは不可能です。担任が子どもの側から離れないようにするには、代わりに保育補助がそれらを行わなければいけないということになります。そうなると、より負担に、より重労働に変わってしまうでしょう。そして、責任の所在もわからなくなってしまいます。
そのため、担任がその場を離れた時の補助は、「一緒に遊びながら、子どもたちから目を離さず、危険を察知しながら」という、役割があります。
その場を一人で任されたけど、不安・・・。そんな方はこの記事で大きな声を出さなくても子どもを集められるポイントを解説しているので、参考にしてみてください。▶︎「大きな声がいらない保育」
安全を作るのポイントは、「できるだけ自分の視界に子ども達を集める」ことです。

雇用形態(パート限定)
パートの求人の相場はこちらです↓
- 賃金は時給(相場は1,000円〜1,500円)
- 手当等あり(早朝や預かり保育・土曜日出勤等)
- 就業時間は7時〜20時の間で5時間未満or5時間以上
- 出勤日数は週3日〜5日
- シフト制
園ごとに違いがあるもの↓
- 時給(地域で最低賃金が異なるため)
- 就業時間(開園時間が異なるため)

知っておきたいポイント!
扶養内であれば、週3日〜5日出勤で、就業時間は5時間程になります。
また、保育園は開園時間が長いため、シフトは午前と午後で分かれることがあります。
パート契約でも担任をすることがある!?
クラス担任を持つことがある!?
担任業務はざっくりとこんな感じです↓
- クラス運営(日々の活動計画・子ども一人ひとりの把握・記録)
- 書類業務(指導案作成・日誌・連絡ノート等)
- 活動準備(手作りおもちゃ・月の製作・室内遊び/外遊びの準備・行事に向けてクラス製作等)
もし、保育補助(パート契約)のあなたが担任としてクラスを任された場合は上記の内容を行うことがあります。
「パートで担任を持つことがあるの!?」と驚かれると思いますが、これは園によります。
雇用形態は変わらないのに、正社員(常勤)と同じ業務量になるということは、「希望していた働き方と違う」「持ち帰りが多い」「負担が大きい」など、様々な不具合が出てきてしまいます。
そのため、希望しない場合は断っていいでしょう。
なぜ、パート契約の人に担任業務を任せるのか、一番の理由は「人手不足」です。新学期が始まるまでに正社員(常勤)を採用できず、今年度は仕方なくパートさんにお願いするという突発的な場合はお願いされることが予想されます。
それ以外の理由でしたら、注意が必要です。例えば、「毎年のようにパートが担任を持っている」など。なぜなら、わかりやすく言うと「正社員(常勤)と同じ責任を背負う」ことになるからです。保育計画の作成などの書類作成を始め、保護者対応、日々のクラス運営、行事のクラス練習・準備など多岐に渡る仕事をこなし、怪我の対応と対策・発熱や突発的な体調不良の対応、事故防止・アレルギー対応その他トラブルの対応など命に関わる負担ものしかかります。
「担任と補助の仕事は分けたくない」「資格を持っているから、同じように責任を持って働いてほしい」と運営側は言うと思いますが、その通りであり、違います。
その通りというのは、保育士資格という保育のプロとしての責任を持っているということです。
違うと言うのは、契約条件が違うということです。
時間給であるパートは、時間内で業務をしなければいけませんが、正社員(常勤)の雇用契約では、「時間給」という規定はありません。なぜパート契約が正社員(常勤)の業務を担えないかというと、保育の性質にあります。
子どもの成長は点ではなく、線で捉えて常に成長発達を見通した計画・関わりが重要です。そのためには日々記録をとり、計画書を作成し、保護者や園と連携をとり、必要なものを準備し、共に生活するという、時間がいくらあっても足らないくらいの保育が必要です。
そのため、時間給の契約であるパートさんが担任業務を任された場合、「業務の負担」と「時間の制限があるというやるせなさ」が生まれます。
そのため、希望していない場合はきちんと断りましょう。
支援が必要な子の専任になることもある
もう一つ、ドキッとすることを言われることがあります。それは、「支援が必要な子の担当」をお願いされることです。
「支援が必要な子」とは、発達障害の診断が出ている子や、障がいの診断は出ていないが個別対応が必要な子も含まれます。園によっては、「気になる子」として、集団から離れて個人行動をする子、他の子を怪我させてしまう子など、そばに保育者がいないと心配な子の専任を任されることもあります。
専任をお願いされる主な理由は、「個別対応が必要」だからです。支援が必要な子の専任をお願いすることは、丁寧な保育をするための工夫でもあります。
もし任されても、心配はありません。他の子と同じように丁寧な1対1の関わりを行えば問題ありません。契約している時間内で、その子に合った配慮と愛情をかけてあげましょう。専任だからと言って、計画書や記録をとる必要もありません。ただ、クラスから離れる場合やいつもと様子が違う場合などは必ず担任に報告しましょう。
保護者への連絡や保育計画を立てているのは担任です。独断で判断せず、担任と方針や対応を擦り合わせながら個別の対応を行いましょう。
もし、自信がない場合は専任の話が出た時に上司に相談しましょう。

まとめ
保育補助の仕事のまとめはこちら↓
- 保育業務と雑務がある
- 年齢によって介助や補助の仕方が変わる(食事やトイレなど)
- 支援が必要な子のサポートがある
- 制作の手伝いを言われた時は細かな確認が必要
- 見守りは「ただ居る」だけではない
- 時間給で働く。相場は1,000円〜1,500円(地域差あり)
- 扶養内の場合は、出勤日数と勤務時間の制限がある
- パート契約でもクラス担任を持たされる時があるので注意
- 個別対応が必要な子の専任になる場合もある
保育補助は、担任との視点が違うことが魅力的なポイントです。子ども目線で保育が見れたり、個別の対応を任されてやりがいを感じたり、保育補助だから発見できる保育の楽しさもあります。
保育士資格を取得した方や仕事復帰を考えている方は、保育補助からスタートだと、家庭との両立もできるので、余裕が生まれます。
他にも、保育補助のメリットはたくさんあるので、ぜひこの記事を参考にして、保育補助にチャレンジしてみてください!