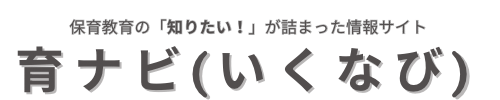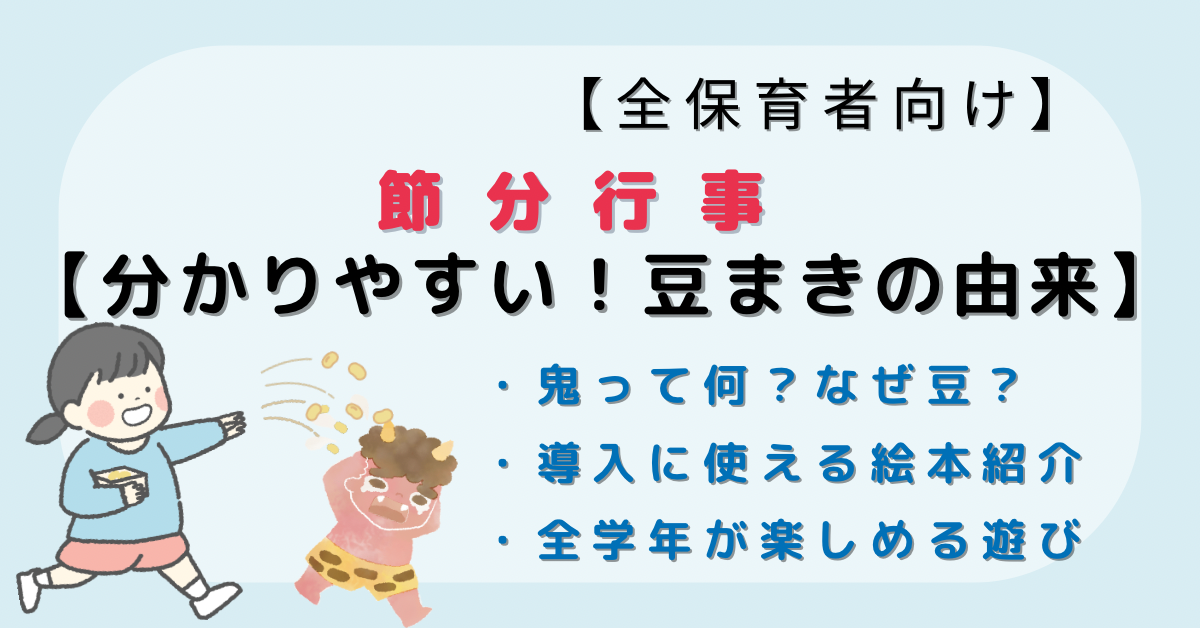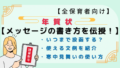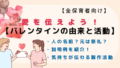こんにちは!はち先生です。
日本の伝統的な文化である「節分」。2024年の節分の日は、2月3日(土)です。
子どもたちにとっては、「鬼が来る」ことが楽しみの子もいれば、怖いと思う子もいると思います。
そもそも、なぜ、「鬼は外、福は内」って言いながら鬼に豆を投げるか知っていますか?
子どもにも分かりやすく伝えられたらもっと節分行事が楽しめそうですよね!
今回は、節分行事の導入に使える絵本と節分の由来について解説していきます!
それでは、どうぞ!

この記事は、こんな人におすすめです。
- 行事担当の先生
- 保育士
- 幼稚園教諭
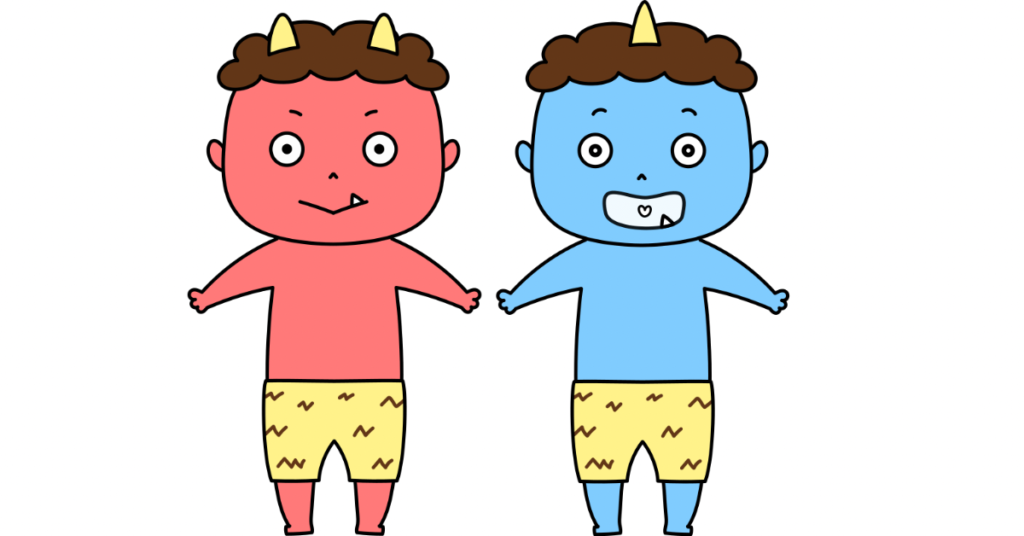
節分の由来
節分って実は1年に何回もある
そもそも「節分」とは、季節の変わり目のことなんです。立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを指しています。
その中でも、旧暦で新年の始まりを表す立春は大切な節目だったため、室町時代あたりから立春の前日を「節分」と表すようになったそうです。現在では、「節分は2月3日」が一般化されたそうです。
節分の夜は、一年の中で大きく様々なことが変化する時であるため、鬼や魔物が出現しやすいと考えられていました。そのため、鬼や魔物を追い払うための行事として「豆まき」ができたと言われています。
節分の日では、病気や災害を追い払う儀式として豆まきを行います。
豆まき
豆まきには、大豆を使いますよね。昔から日本では、米や麦、ひえ、あわと並んで大豆には穀霊と呼ばれる精霊が宿っていると考えられています。大豆はその中でも粒が大きいため、鬼退治に適しているため豆まきに使われるようになったとか。
年の数だけ食べる
「豆を年の分だけ食べると健康でいられる」と聞いたことがありますが、食べ方はご存知ですか?
豆まきの後に、「年の分だけ豆を食べる」のですが、一般的な食べ方は、「自分の年+1つ分の豆を食べる」です。これは、「年取り豆」と言われ、1年の厄除けを願う風習です。
地域によっては、年取り豆の食べ方に違いがあるため、その地域のやり方を実践されるといいでしょう。

ちなみに私は、地方出身ですが、「年の分だけ食べる」と認識していました。
関東の幼稚園で働いたときは、「年の数プラス1つ」と教わり、違いに気づきました。
子どもへの伝え方
大昔から鬼は災い、大豆は縁起が良いものとされてきました。子どもに分かりやすく説明するなら、こんな伝え方はいかがでしょうか?
- 鬼が来ると病気や悪いことが起きるから、豆で退治するんだよ。大豆には鬼を退治する力と、いいことを呼び込む力があるから、「鬼はーそと!福はーうち!」って言って投げるんだよ。
- 悪いものを追い払って、良いものを呼び込むために豆まきをするんだよ。
- 鬼さん来ないでね、良いことがたくさんありますようにって願いながら豆まきをするんだよ。
- 大豆には、栄養がたっぷりだから、1年健康でいられるように食べるんだよ。
節分や豆まきの意味を知ると、子どもの「なんで?」にも答えられやすくなりますね。
年齢別導入絵本
0〜2歳児
構成・絵:鈴木博子「おにのパンツ」
童謡の「おにのパンツ」の歌に合わせて絵が展開されます。子どもと歌いながら体も動かせる絵本です。
私も持っているのですが、乳児さん担任していた頃は重宝していました!
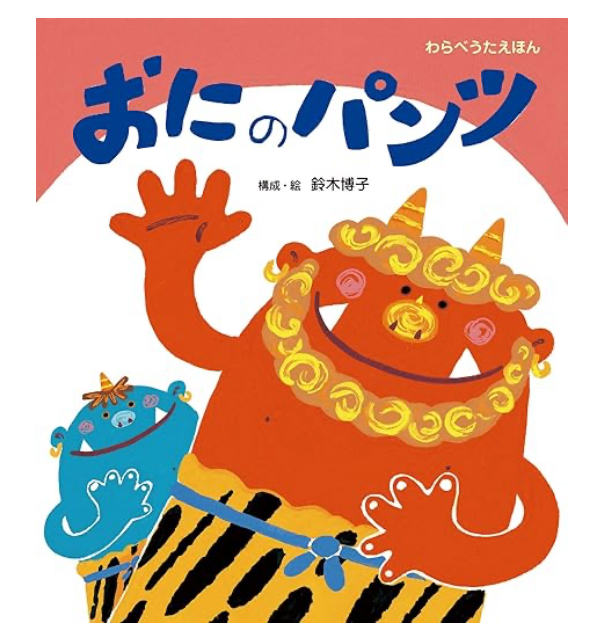
2〜3歳児
作:ますだゆうこ 絵:たちもとみちこ 「せつぶんワイワイまめまきの日!」
カラフルな絵に目を奪われちゃいます。手書き感があるイラストのため、製作の題材や導入にも使えそうです!
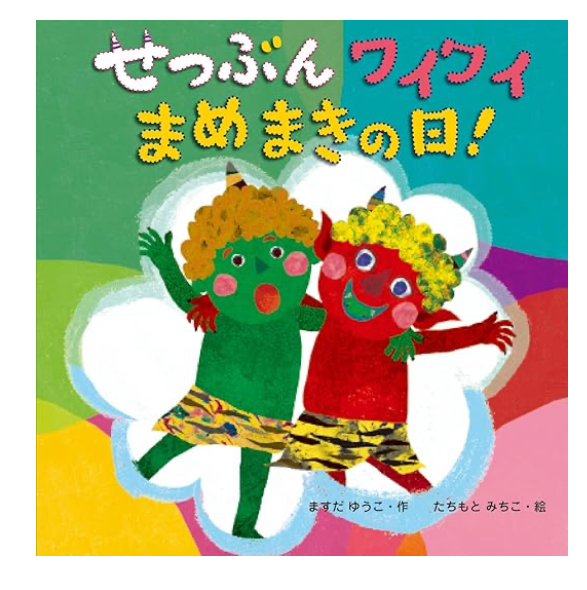
4〜5歳児
文・絵いもとようこ 「おにはそと!ふくはうち!」
豆まきの由来がわかる絵本です。どうして「おにはそと! ふくはうち! 」って言うのか、どうして豆をまくのかが分かるので、じっくり読み聞かせるのにもってこいな絵本です。
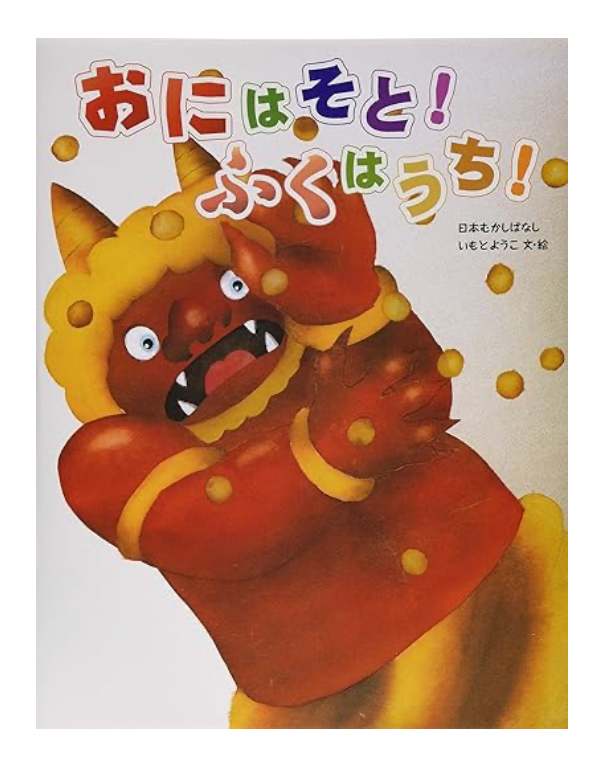
乳児から幼児まで楽しめる簡単あそび
玉入れ遊びを節分バージョンにしてみました!
豆は、子ども達と新聞紙を丸めて作れば、当たっても痛くない豆の完成です。
先生がダンボールで作った鬼を持って戸外や広い部屋・ホールで逃げ回ります。
先生側は結構ハードですが、子どもたちは大喜びです。年長さんには、段ボールを使って自分たちで鬼を作って、チーム対抗で遊ぶのも楽しそうです!

材料はこちら↓
- ダンボール(サイズバラバラで作るものいいね!)
- 画用紙
- のりOR薄めたボンド
- 新聞紙(豆用)
私は、豆に折り紙を貼って得点を色別にしたり、おにぎりを用意して変わり種を作ったりしました。
様子を見ながら変化球を付け加えると長く楽しめます!

まとめ
節分を分かりやすく伝えるポイントはこちら↓
- 節分とは、季節の変わり目のこと
- 鬼は病気や災害に見立てられていた
- 豆は縁起が良いものだから、鬼を退治できて、福を呼び寄せる
- 年の数だけ豆を食べるのは、地域によって違いがある
- 絵本で導入すると分かりやすい
- ダンボールで楽しい豆まき遊びができる
育ナビの記事を参考にしながら、楽しい節分行事にしてください!