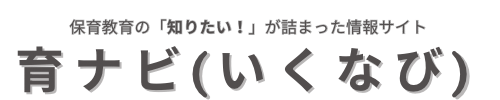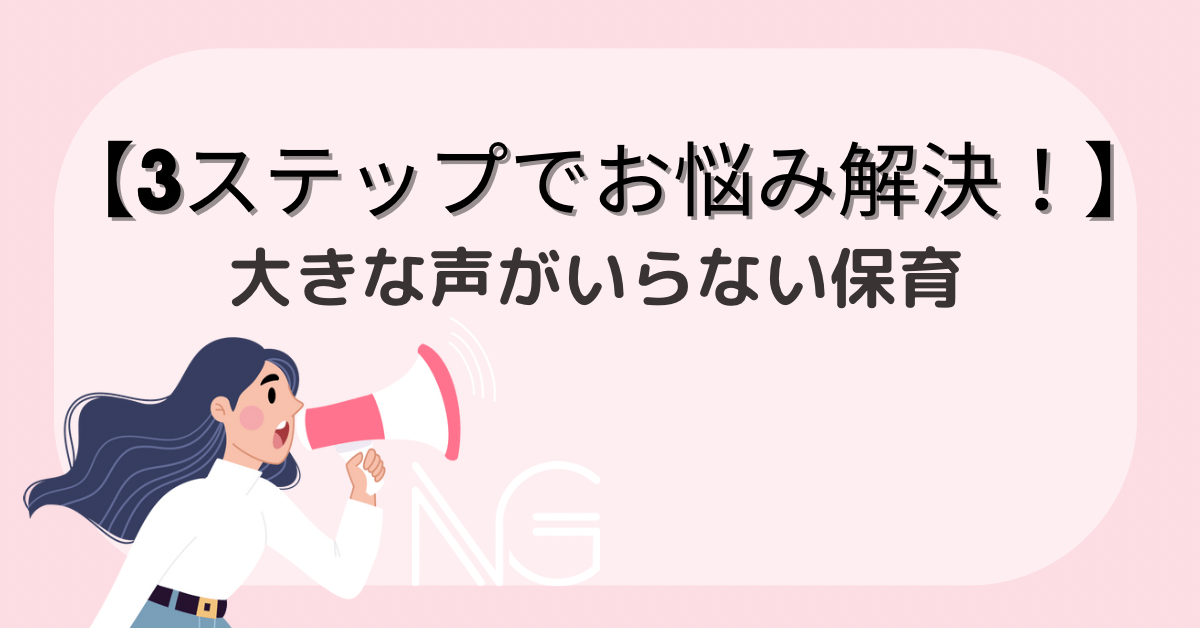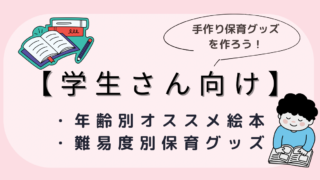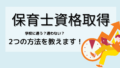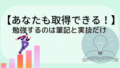こんにちは!はち先生です。
保育学生さん、担任を持っている保育士さん、幼稚園の先生は、こんなお悩みはありませんか?↓
- 教育実習で子どもが集まってくれるか不安
- 自分の声が遠くまで通らなくて子どもが集まらない
- 風邪をひいたらしばらく喉が治らなくて声が出せない
- 大声で子どもを集める保育をしたくない
上記の中で一つでもチェックが付いた方は今すぐこの記事を見て、悩みを解決しましょう!
私は、全て経験してきました。元々、声が通りにくい&喉が弱いので、保育の中でどうやって子どもとコミュニケーションを取るか試行錯誤してきました。
また、職場に1人はいますよね。“大きな声で保育する先生“。一見、元気に子どもと接しているように見えて、子どもや大人には、大きな声=威圧的な印象を与えます。
過去に複数担任と1人担任を経験した私が編み出した「大きな声がいらない保育」を伝授いたします。
この記事では声で悩む保育を3ステップの方法で解消していきます。
それでは、どうぞ!

この記事はこんな人におすすめです。
- 保育士になってまだ浅い人
- 声が通りにくい人
- 実習を控えている学生
- 現場で働いている先生
- 子どもの注目を集めたい人
※この記事では、教室内で自由遊びをし、次に朝の会などの活動が控えていることを想定しています。

ステップ1 手遊び・歌で注目を集める
まずは、手遊びで近くにいる数名の注目を集めましょう。
定番の手遊びはこちら↓
- グーチョキパーでなにつくろう
- とんとんとんとんひげじいさん
- やきいもグーチーパー
- キャベツのなかから
- バスにのって
これらの手遊びはアレンジがしやすく、子どもの様子に合わせてリズムや声の大きさに強弱をつけたりできるので、オススメです。

私が保育でよく使うのは、「グーチョキパーでなにつくろう」です。わかりやすい手の動きと“何が出てくるんだろう“というワクワクで子どもたちが注目してくれます。0歳児さんには、グーとグーで「アンパンマン♪」にすると大喜びです。5歳児さんには高度なグーチョキパーを見せましょう。スピードアップして「先生についてきて!」というと、必死についてきてくれます。子どもと一緒にグーチョキパーのアレンジを考えてもいいですね。
とんとんとんとんひげじいさんはアレンジが多様です。最後に「キラキラキラキラ てはおひざ」「てはおくち しー」など、声をだんだん小さくしたりなど、口元に人差し指を当てるジェスチャーをすると子どもたちは真似をして静かになりますよ。

ここでワンポイント!
立ち位置を工夫しよう
さらに、子どもが注目する先生の立ち位置をお伝えします。手遊びの力は偉大ですが、プラスで自分の立ち位置も変えてみましょう。どんな先生でもあっという間に子どもが注目してくれます。
立ち位置のポイント↓
- 子どもが集まっている場所に自分が移動して手遊びをする。
- 壁を背にして行う。
解説をしていきます。
ポイント1 「子どもが集まっている場所に自分が移動して手遊びをする」
声が通りにくい場合、自分から子どもの輪に入っていきましょう。そこで手遊びが好きな子どもたちとやり始めるのも一つの工夫です。その後、周りの子が興味を示して集まってきてくれます。
この時、実習生さんや経験の浅い先生に見られるのは、小さな声で少人数と手遊びをしているです。
子どもたちと個別でコミュニケーションをとっている時はOKですが、今回は、“子どもたちを集める“のが目的なので、次の行動や活動がある場合は、子どもが注目する・できるだけ大人数を惹きつけるを意識しましょう。
補助の先生・実習生さん・経験の浅い先生は、この方法でリーダーの先生のサポートしてみてください。リーダーの先生はとても忙しいので、「今は手が離せないけど、子どもたちを集めなきゃー!」と思っている場面が多々あります。その時に、ステップ1を他の先生がしてくれて、子どもたちを集めてくれていた時には「ありがとう!!」と称賛の嵐です。担任の先生とコミュニケーションをとって、“活動の前に子どもたちを集めても良いか“を確認しておきましょう。
ポイント2 「壁を背にして行う」
壁を背にすることで、自然に子どもたちは自分の前に集まります。さらに、背景がシンプルな壁側の方が◎です。先生の背景に気になるもの(おもちゃやキャラクターの絵等)があると、そっちに気を取られて注意散漫になってしまうので注意しましょう。
※子どもに背中を向けるのは避けましょう。事故防止にもなります。
もしご自身が環境設定できるのであれば、教室の壁の1面はできる限りシンプルにしておくと良いです。お集まりの時や子どもに話す時は必ずその場所と決めておくと、子どもたちも“集まる場所“と覚えてくれるので新学期の時期から習慣化すると良いでしょう。
そしてこの方法は、複数担任または補助の先生が数名入っている場合には、とても有効です。なぜなら、どの先生が手遊びをしても、声をかけても、子どもたちが“この場所は集まる場所“と覚えているので「なんだ?」と注目して集まってくれます。
もし自分がクラスのリーダーを任されている場合は、環境設定と習慣化で、自然に子どもが集まる仕組みを作っておきましょう。
ステップ2 絵本・パネルシアター等で聞く姿勢に
手遊びで子どもたちを惹きつけた次は、視覚的に楽しめるものを用意しましょう。
視覚的に楽しめるものは集中しやすいですし、ページや場面が変わることで飽きずに見ることができます。
子どもに人気の絵本はこちら↓
- はらぺこあおむし
- だるまさんが
- おべんとうばす
- わたしのワンピース
- 大きなかぶ
今回は絵本の紹介ですが、他にも紙芝居・パネルシアターなどがあります。
現場でも使える年齢別オススメ絵本をまとめた記事もご参考ください。
乳児(0〜2歳児)クラスの場合
乳児クラスは1クラスの人数が10人弱なのでコンパクトな絵本でも全員が見れますし、動きが多い年齢なので、コンパクトな絵本の方が読み手の先生もとっさの対応が可能です。
よくあるトラブルは、急に嘔吐してしまった、子ども同士のケンカが起きたなどです。その時に大きな絵本や紙芝居の台などを使用していると、「対応しようと動いたら絵本の角がぶつかってしまった」などの二次被害を生んでしまう可能性があります。
乳児さんにオススメは、他にも「だるまさんが」シリーズや「ノンタン」シリーズ、「おべんとうばす」、「しろくまのパンツ」、「ぼうしとったら」などの仕掛け絵本も大人気です。
乳児クラスで大型絵本などを読みたい場合は、他の先生と連携をとりながら、安全を確保した状態で読みましょう。
幼児(3〜5歳児)クラスの場合
幼児クラスでは、大型絵本が◎。1クラスの人数が20〜30人程なので大きめの絵本だと奥にいる子や端の子も見やすいです。年齢や時期に合わせて内容が深い話やページ数が多いものを選ぶと良いでしょう。
幼児さん向けにさらに保育のワンアップ情報です。子どもの「聞く力」を伸ばせて他の先生からも一目置かれちゃいます!
それは。素話(すばなし)です。素話とは、絵本や紙芝居と違って、小道具を使わないお話のことを言います。子どもへの効果は、①集中力がつく ②想像力豊かになる ③言語能力やコミュニケーション能力が身につく などがあります。昔話や童話を保育士が言葉だけで話します。落語家さんや寝る前にお母さんが昔話を聞かせてくれるイメージです。子どもは、絵を見ないので、先生に注目したり、目をつぶって物語をイメージするため、「集中させたい時」「お昼寝の前にリラックスしたい時」などに活用するといいでしょう。手遊びで静かになった後に素話を持ってくると、先生の声が小さくても子供達は聞こうと集中してくれます。これも習慣化するとなおGOODです。ポイントは、短い話でいいので話す側は物語を記憶するということです。ぜひ試してみてください。
幼児さんにオススメは、「11ぴきのねこ」シリーズ、「もったいないばあさん」、「めっきらもっきらどおんどおん」など少し変化球で怖いお話も人気です。

ワンポイント!
準備をしよう
絵本はあらかじめ用意して側においておくとGOODです。
よくあるのは、手遊びが終わってから慌てて絵本を探しに行くと、絵本を取りに行く先生の動きが気になってしまい、それまでの集中がプツンと切れてしまったり、年齢が低いまたは新学期初めだと「もう終わりかな?」「遊んでいいのかな」と思い、遊びだしてしまうことがあります。
今回の場合は、手遊びで注目を集め、絵本によって話を聞く体勢を整え、次の行動に繋げるということが目的です。そのため、その日のリーダーや主で動く先生はなるべくその場から離れないことを意識してみてください。この方法は、実習生の方や経験の浅い先生などには特に有効です!

「なぜ子どもたちを集めたいか」「その後の活動に繋げたいか」など目的をもった自分の行動は、一貫性の印象を与えるので、子どもたちにもわかりやすく、覚えやすいのでルーティーンとして定着したり、子どもたちの情緒や生活の安定につながります。
子どもたちに混乱が起きないように、手遊びをする=「これから楽しいことが始まるかも」というイメージや雰囲気を作りましょう。
ステップ3 お話しをする
ステップ1〜2が終わった頃にはほとんどの子が自分の声に耳を傾け、目の前に集まっているはずです。
そして静かになっていることでしょう。この時がチャンスです!声が通らない方は、場が静かになった時に全体に向けた話をすると声を無理に張らなくても、声が届きます。それは聞いてくれる姿勢が整っているためです。また、まだ遠くで遊んでいる子もいるでしょう。個別対応が必要な子には、このタイミングで名前を呼ぶことをおすすめします。ざわざわしている時に呼んでも来ない場合は、その子は自分のことだと認識せず聞こえていない可能性があるからです。
視覚的な表現を使う
「声が通らない・緊張する・声が届くか不安・風邪を引いていて声が出せない」
このような場合はこんな方法を使って、みてください↓
- ホワイトボードで説明する
- 画用紙やA4用紙、模造紙などにイラストや文字を書く
- パネルシアターを使う
これらは私が実践してきたことです。黒板などのボードがある園はなかったので、自分で黒板のようなものを作って、そこにイラストなどを貼った時もありました。特に便利だったのは、パネルシアターです。台を折り畳められるようにすればコンパクトに収納できますし、貼ったり剥がしたりすることが可能です。劇を教える時に活躍しました。ホワイトボードも使い勝手がよく、さっと出せるので一枚持っておいてもいいでしょう。使い方は、ちょっとしたコミュニケーションや空いた時間に絵を描いてクイズにしたり、図を書いて説明したり、消して書き直せるので便利です。
ワンポイント 無理はしない
注意することは、無理に全員に話を聞かせようとしないことです。人数や年齢、関係性や状況にもよりますが、クラスの子どもたち全員が座って自分の話を静かに聞いているという状況はほとんどありません。
誰か1人は端っこでまだ遊んでいる状況の方が多いです。
しかし、その1人を除いてはクラスの大半の子どもが先生の顔を見て、「次に何を話すのか」待っています。先生の動きもよく見ています。そのため、すでに“話しを聞く体勢“になっている子どもたちのことも考えることが大切です。
「手遊びをして、絵本を読んで、これから始まる楽しいことを知る」という流れ・目的は崩してはいけません。
話を聞いてくれる大勢を整えたのならば、まずは目的を果たしましょう。それは「今日の予定を伝える」などの目的です。
1人で遊んでいる子などの対応は、「3回名前を呼んでも来なかったら他の先生にお願いしよう」「近くに居てくれたらO K」など自分の中でルールを決めて、他の先生と連携しましょう。

まとめ
3ステップのおさらい
- 手遊び・歌で注目を集める
- 絵本・パネルシアター等で聞く姿勢にする
- お話しをする
手遊びや絵本選びは、年齢に合ったものだと集中してみてくれます。手遊び→絵本の流れでは効果的な手段を選びましょう。
伝えることや話すことが苦手なら、視覚的に伝えましょう。例えば、ホワイトボードや紙にイラストを書いたりするなど。絵カードなども◎
目的を見失わずに、無理はしない。全員に話を聞いてもらうことはほぼ無理です。先生の話を待っている子もいるということを理解し、信頼関係のためにも、保育者は自分の行動に一貫性を持たせることが重要だと考えます。「集めた理由は?」「伝えたいことは?」と目的意識を持って行動してみましょう。
そして、話を聞いてもらえるように工夫できるのは、日頃のコミュニケーションと習慣化です。
保育士になって日が浅い方、補助をしている方、急に「朝の会の前に子ども集めてください」って言われて困った方、子どもの注目を集めるにはどうしたら良いか悩んでいた方はぜひ参考にしてください!
明日からの保育のレベルがアップすること間違いなしです!