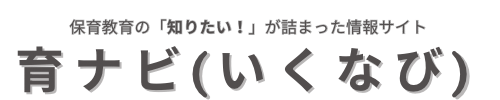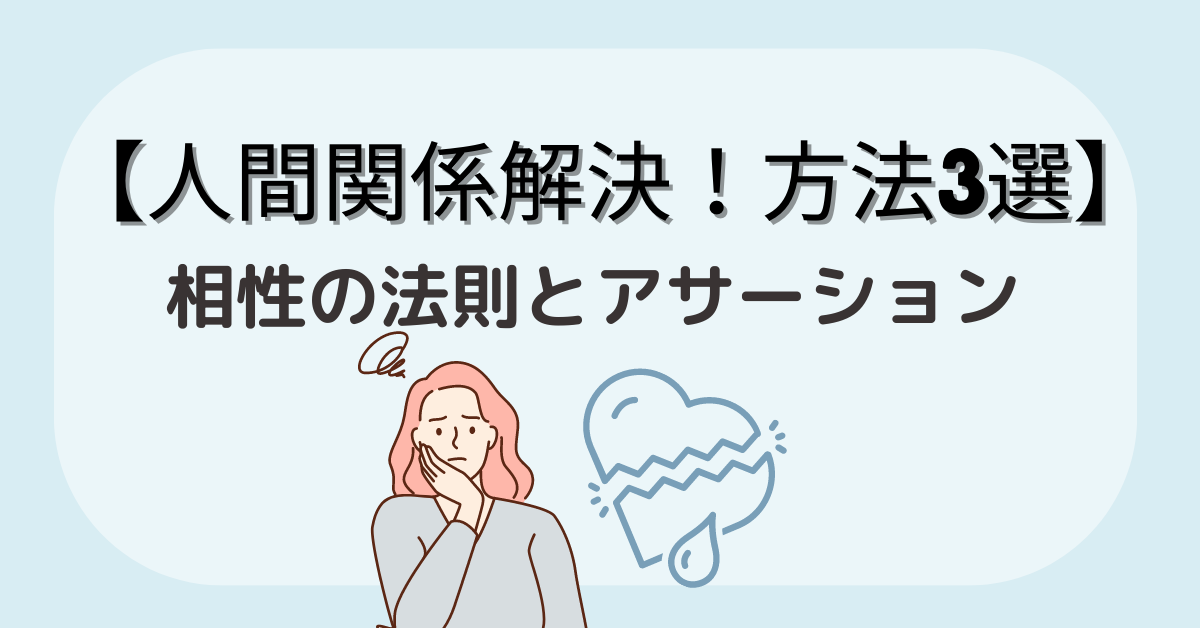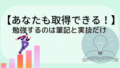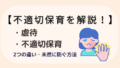こんにちは!はち先生です。
新人の先生、怖い先輩と組んでいる先生、人間関係で心を病んでいる先生、保育の大人社会は嫉妬やマウント、過度な上下関係など悩みが尽きませんよね。純粋無垢な子ども社会がキラキラして見えてしまうことはありませんか?
例えば人間関係でこんなことに振り回されていませんか?
- 「子どもたちにはキラキラの笑顔!」裏では「大人にイライラ嫌悪剥き出し笑顔」の先生
- 「職員室はいつも不穏な空気が漂っている・・・」
- 職場でグループができていて関わりづらい
- なぜか自分にだけ当たりが強い先輩
- 体裁を必死に守る上司、お気に入り先生を贔屓(ひいき)する上司
保育・教育は少し特殊な職業です。先輩や上司、お局さんに気を遣いながら、子どもには笑顔で接するなど、対応を使い分けをしなくてはなりません。日々の業務にも追われ、大人の複雑な人間関係に疲れ、情緒が不安定になることもこの職業では多いです。退職や転職をする理由も人間関係の悩みが8割。
今回は、保育者として日々頑張っている先生たちの悩みを解消すべく、人間関係不器用な私が、様々な心理学や人間関係の本を読み漁って、「これは使える!」と実際に実践して良かったものを紹介します。
この記事を読めば、明日から人間関係に振り回されず、心軽く仕事ができるようになりますよ!
それでは、どうぞ!

この記事はこんな人におすすめ
- 人間関係で苦しんでいる人
- 入職してすぐに退職していいのか悩んでいる人
- コミュニケーションの取り方のヒントを知りたい人

解決方法① 相性の法則を知る
人間関係には「相性」があり、「法則」が存在することをご存知ですか?それが「相性の法則」です。
誰にでも苦手な人はいます。そして、どんなに努力しても、苦手な人をなくすことはできないです。
転職しても、自分が苦手とする同じようなタイプの人は必ず1人は現れます。その人から嫌われないようにと気を使うと、逆に振り回されて自分が傷ついたり、好かれようとすると疲れてしまったり、また人間関係に悩んでしまいます。
しかし、苦手な人に無理に好かれようとしたり、嫌われようとしたりしなくてもいいんです。
なぜなら、人間関係の相性の法則があるからです。では、紹介しましょう。
2:6:2の法則
相性の法則は「2:6:2」です。
- 2 自分のことが好きな人の数
- 6 自分のことをなんとも思っていない人の数
- 2 自分のことを嫌いな人の数
私は、心理学やヨガの勉強をしている時にこの法則に出会い、衝撃を受けました。「ほとんどの人は私に興味ないんだ!」と。極端な捉え方だったかもしれませんが、その時にそう思ったことで心が楽になりました。
なぜならそれまでは、(全ての人に好かれなきゃ)(なぜこの人に私の話が伝わらないんだろう)(なぜこの人は意地悪なんだろう)と1人で悶々と考えて必要のないストレスを抱えていたからです。しかし、それらは全て自分の思い込みだったのです。
その後、私はこう考えました。
- 2 家族や恋人 自分の味方になる人が2人もいるんだから大丈夫
- 6 職場の人はほとんど自分に興味のない人だと思って、細かいことを気にする必要はない
- 2 自分も苦手な人がいるから、自分を嫌いな人もいるよね 2人くらいは別にいいじゃん
どの職場にも同じような苦手だと思う人は現れます。そんな時は、「今、自分を取り巻く人間関係の8割の中には、味方が2割で、6割はどうでもいいって思っている人だから気にすることない」と心で唱えてるようにしています。
「みんなに好かれたい」と思うことは誰にでもある素直な気持ちだと思います。特に、子どもを相手にする先生という仕事は、信頼関係の構築が最も重要な職業です。愛情深い人が多く、子どもに向ける愛情を行動で示すことで信頼関係の構築につながります。そのため、「子どもに好かれたい」という気持ちを持つことは保育者にとって当たり前の感情だと考えます。
しかし、大人社会で良好な関係を築くには、コミュニケーションスキルが必要になります。(解決方法②で紹介します)
「自分の愛情(又は助言など)を受け取ってくれない」と思うときは、相手は受け取る心の準備ができていない又は今は必要ないと思っているのだと思うことにしましょう。あなたに興味がないわけでも、あなたが嫌いなわけでもありません。受け取り手の課題です。
この考え方は、子どもも大人も同じです。相性の法則だと、自分のことが苦手な人が2割いて、6割はどうでもいいと思っているので、あなたが自信をなくす必要はありません。
「2割の苦手」に執着してしまうと人間関係の渦に迷い込んでしまうので、できる限り良好な関係を築きたいですね。そんな方には次のような対応の仕方があります。
2割の苦手の対応
- 積極的に関わってみる→関係が改善されるかもしれない
- 距離を保つ→割り切りも大切 ※挨拶などの最低限の礼儀は忘れずに。
苦手な人と良好な関係を築きたくて、思い切ってサシ飲みに誘ったことがあります。しかし、自分1人が空回りして、関係が悪化したと感じた時もありました。むしろ関係がマイナスになったことの方が多かったと思います。
そんな失敗から、こう考えるようにしました。
「無理して良好な関係を築こうとしなくてもいいけど、マイナスが増えない対応をしよう」
マイナスというのは、①仕事の報連相が取れなくなる ②溝が深まり人間関係が悪化する などです。
マイナスが増えると自分の仕事にも影響が出ます。そうならないためにも、小さくても改善できることは自分から行動してみましょう。

最低限これだけやっていたら関係を悪化させない!
それは・・・
- 挨拶をする(おはようございます。お疲れ様です。お先失礼します。)
- 報連相は怠らない(報連相を怠ると命に関わるミスにつながる!それだけは阻止しよう)
最低限、上記の2点だけをしていれば問題ないです!
解決方法② 大人社会で生き抜くコミュニケーション術
次は、コミュニケーションの仕方について説明します。相性の法則の最後に「小さくても改善できることは自分から行動してみましょう」と言いました。私は一時期とても人間関係に悩み。藁をもすがる思いでこのコミュニケーションを実践しました。初めは声をかけるのでさえ怖かったですが、この手段は自分にとってメリットしかないと思い、心がけていました。
複雑な大人社会、女社会が苦手な人もこのコミュニケーション術を使えば、明日から人間関係が楽になりますよ!
では、具体的に有効な方法をお伝えします。それは、「アサーション」(自分を大切にし、相手を配慮する表現方法)です。それでは、アサーションについて説明していきます。
アサーションとは
- 自分も相手も大切にする自己表現法
- もともと、人間関係が苦手・引っ込み思案でコミュニケーションが下手な人を対象にしたカウンセリング方法・訓練法
- アメリカの心理学者ウォルピーが開発
自己表現の3タイプ
自己表現には3つのタイプがあります。あなたの周りにいる人、あなたは何番に当てはまりますか?そして、あなたは何番に近づきたいですか?
- 非主張的自己表現=自分よりも他者優先。自分は後回しにする。
- 攻撃的自己表現=自分のことだけ優先。時には他者を踏みにじることにもなる。
- 他者のことにも配慮する自己表現=①と②のちょうどいいバランスであり、自分のことも考えるが他者のことにも配慮する=アサーション
自己表現の3タイプは、人は必ず100%どれかに偏っているわけではなく、無意識に3つのどれかの表現を使っていて、その割合は人それぞれだそうです。
今回のこの記事では、人間関係に関するお悩み解消が目的なので、早速具体的な表現方法を説明します。私もこれの表現を知ってから人と話す時、会議などの意見を出す場で実践したり、意識しています。
アサーティブコミュニケーションの実践
相手を傷つけることなく、自分の気持ちを表現できるアサーティブコミュニケーションは、ビジネスの場でも注目されています。
以下の順番で自分の意見を伝えると効果的だそうです。
- 繰り返しで理解を示す
- 状況などを簡潔な言葉で伝えて、事実を述べる
- 感情を分けて述べる
- 現実的かつ具体的な提案する
- 「助かる」「嬉しい」などの提案の効果を端的に伝える
ℹ︎メッセージを使う
周りの先生の話し方を聞いていると、相手を主語にした言い方をする人を見かけます。
その先生から受ける印象は「きつい」「怖い」「威圧的」です。例えば、こんなNG表現です↓
- なんで、〜しないんですか
- 〜しないで
- 早くして
こんな言い方では、子どもも大人もその人の話を聞きたくないと思ってしまいますよね。
しかし、言葉の主語を「ℹ︎(アイ)」に変えるとポジティブな印象に変わります。
- 私は〜してほしい
- 私はあなたに急いでほしい
- 私はあなたに〜してくれると助かる
いかがでしょうか。主語に「私は」を加えるだけで、相手を責めているようには聞こえないけど、自分がどうしてほしいのかを伝えることができます。
他の方法を2つ紹介
他にも方法が2つあります。
- 代替案を出す
- 「Yes and」を使う
1、代替案は、「こうしてみたらどうでしょう?」と代替案をセットにして提示することで“ただ文句を言っているだけではない“ということを相手に表すこともでき、全体のこと・みんなのことを考えているという姿勢も見せることができます。
2、「Yes and」は、話し合いの時に「いいですね」と相手の意見を受け止めた上で自分の意見を述べる表現です。「いや」「そうじゃなくて」と間髪入れずに言ってしまうと相手に「この人には話したくない」という印象を与えてしまいます。グループで話し合っている時には雰囲気を壊してしまう恐れもあります。「いや」「でも」などの口癖がある方は「いいですね」と一度受け止めてから、「〜するのはどうですか?」と意見を出すのがいいでしょう。
私の実践・効果
これまで紹介したアサーティブコミュニケーションは、実際に使って効果がありました。
例えば、企業主導型保育施設の立ち上げを経験した時、法人の代表に収支プランや採用、設備にかかる費用など様々な資料を作りプレゼンテーションを行いました。
相手は病院を経営している一番偉い人たちです。20代半ばの保育士がどうやって話を聞いてもらうか、予算が下りるのか頭を悩ませました。時間をかけ、複数のパターンを算出して資料を作っているため、目を通してもらい、実行まで繋げなければいけません。その時に取った資格(病児保育スペシャリスト※現在は発行しておりません)に「アサーティブコミュニケーション」が書かれていました。
「これだ!」と思い、すぐさま実践しました。
まずは相手の考えをうなづきながら理解を示す。状況を簡潔に伝えて事実を述べる。そして一番のポイントは「感情を分ける」ことでした。感情を分けて話すのは相手によります。それは、相手が感情論で伝わる人か理論で伝わる人か見極めることです。差別的な表現になってしまいますが、男性は理論でアプローチ、女性は感情でアプローチすると商談ごとは進みやすいと思います。その人の立場(経営者・経理関係等)にもよりますが、幼稚園で働いていた時も相手のタイプによって伝わりやすい話し方を心掛けました。男性の園長や男性職員には理論的な話し方の方が希望を聞いてくれたり信頼関係を作りやすかったと感じます。
結果的には、収支のプランが通ってGOサインをいただき、保育所開設が実現しました。
重要なのは、どんな職業も良好な人間関係の上に質の高い仕事があるので、「その場が良ければいい」「言いくるめられたらいい」のではなく、誠実さを言葉や表現で伝えること、相手を配慮した伝え方と自身の意見をきちんと話すことだと思います。

解決方法③ 相談相手を作る
これまで話してきた解決方法①〜②は個人でできる実践方法でした。しかし、1人で悶々と悩んでいては気付かないうちに過去の私のように体調を崩しそれに伴って精神状態も不安定になってしまいます。
悩み出したら、まずは信頼できる人に相談してみましょう。しかし、その時も「相性の法則」は忘れないように。精神が落ち込んでいる時は「聞いて欲しかっただけなのに」「なんで味方になってくれないんだろう」とマイナスな方へと引きづられていきます。期待しすぎず、心が健康なうちに相談してみてください。
以下に当てはまる人に相談してみるとGOOD
- パートさん(パートさんは時間帯で勤務なので人間関係を割り切っている人が多い・主婦が多いため経験豊富でアドバイスをくれる)
- 事務や雑務をしてる人(長く働いている人も多いので、その園の人間関係に詳しい・客観的なアドバイスをくれる)
- 苦楽を共にした同期や先輩(自分のダメな部分も見せてるため、思い切って相談するとGOOD)
相談時の注意
注意点があります。それは、「公共の場で行き過ぎた発言をしないこと」です。
皆さんが働いている環境は、子ども・保護者を相手とする信頼第一の世界です。いくら悔しいことがあっても苦しいことがあっても、その時の感情で発した言葉が誤った情報となって拡散された場合、混乱が起きてします。自分は働きづらくなり、園にも迷惑をかけたりしてしまいます。一度下げた信頼を取り戻すのは難しいです。そのため、いくら悔しくても苦しくても、歯を食いしばって唇噛んで、その場から去って一度落ち着きましょう。
その時の我慢があなたを守ることになります。
悔しい思いをする前に、自分でできる改善方法を少しずつ実践し、2割の味方を見つけておきましょう。
一年目のつらさ
新人のうちは本当に辛いことばかりですよね。仕事も覚えないといけないし、子どもたちや保護者と信頼関係を築くことに精一杯なのに、職場の人間関係にも気を張らないといけない。
「一年目」というだけで新卒も中途も関係なく、先輩たちは「わからないんだから何を言ってもいいだろう」「わからないんだからこっちの言うことをきけ」そんな雰囲気や気持ちが少なからず裏にはあると思います。実際に、自分が先輩という立場になると「この業界は初めてだから、教えてあげよう」と思うし、自分が指示したことではない行動をとっている姿を見ると、「なんで指示していないのに動いているんだろう」と思ったこともありました。
しかし、そのような一年目の辛さは、相手と自分の立場の違いから起こる考えのズレです。
新人側は「頑張ろう!」「こういう保育がしたかったんだ!挑戦しよう!」と前向きな気持ちに対し、先輩側は「自分の言うことを守ってほしい」「ミスをしたら責任がくる」と感じているかもしれません。
立場の違いから起こる考えのズレを合わせていくには、お互いの歩み寄りが必要です。
新人さんも経験のある先生も、コミュニケーションでの悩みがあるなら、少しでも試してみてください。
まとめ
解決方法3選はこちら↓
- 相性の法則を知る
- アサーティブコミュニケーションを知る
- 相談相手をつくる
相性の法則は2:6:2です。思い悩まず、気楽に人間関係を見ていきましょう。
自分の言動を少し変えるだけで、相手に話を聞いてもらえたり、伝えたいことが伝わります。
味方を作りましょう。しかし、職業のことも配慮した相談場所で相談しましょう。
私も、これまで職場の人間関係にとても悩んできました。上司には「うまくやりなさい」と言われ、「うまくやる」ということがわからず、心理学の本を読み漁っていた時期があります。
苦手な先輩と毎日顔を合わせる、話さないといけないことがプレッシャーになり、緊張状態が続きました。しまいには休憩中に食べるご飯も喉を通らなくなり、生理も来なくなり、自分の体に起きた変化が怖くなって転職を決意した経験もあります。
人間関係に悩み、社会人10年目でようやく「うまくやる」の意味がわかってきました。人ぞれぞれの「うまくやる」の考え方があると思いますが、私の「うまくやる」は、良好な人間関係を保つコミュニケーションスキルをつけるということだと思いました。
人間関係に悩む先生たちはこの記事をぜひ参考して、明日から実践してみてください!