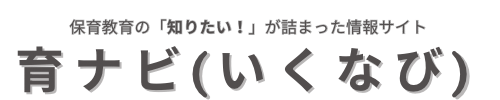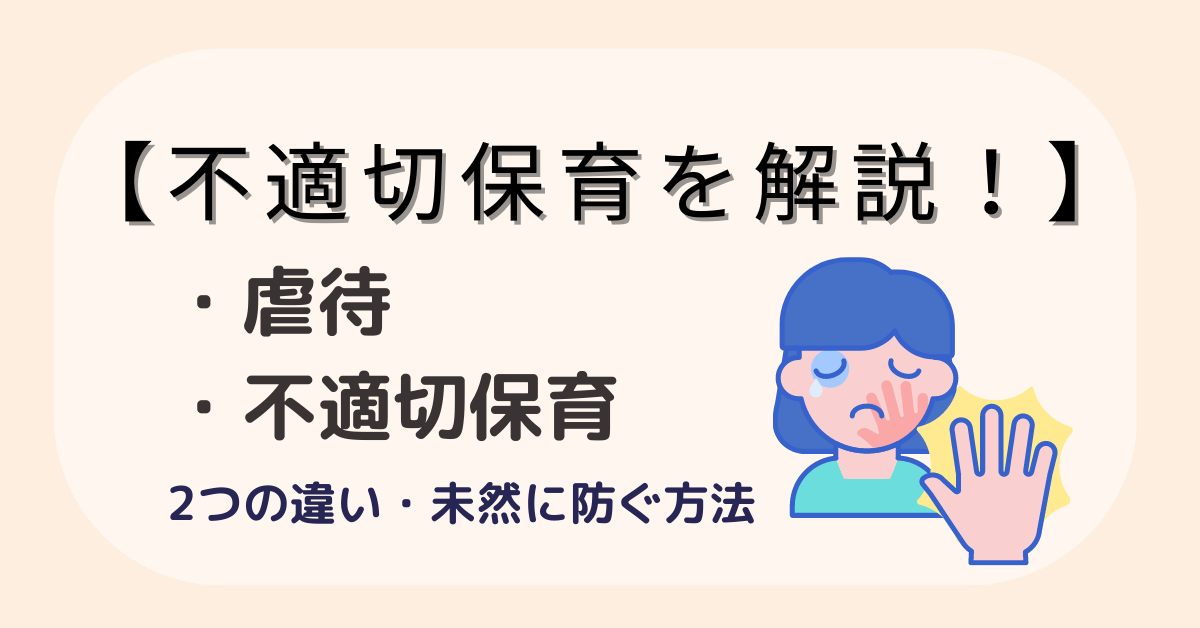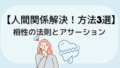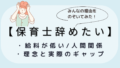こんにちは!はち先生です。
保育士・幼稚園の先生なら一度は、「あれ?この保育は適切・・・?」と思った瞬間ってありますよね。例えばこんなこと↓
- 0歳児の子どもに大声で急がせる
- 食事介助で無理やり口に運ぶ
- 子どもの羞恥心が守れていないトイレ・プール環境
- 子どものことを無視した自分本位な行動・保育
希望をもって入職したはずなのに、周りで起きている保育を見て、「これっていいの?」と理想と現実の違いに衝撃を受けることもあります。
これを見ているあなたは、「これっていいの?」という違和感を解消したくて、この記事に辿り着いたのだと思います。
現役の先生はドキっとしたかもしれません。もしかしたら、あなたの当たり前だと思っていることが「当たり前ではない」ことだったかもしれません。
子どもへの不適切保育・虐待についてガイドラインが存在することをご存知でしょうか?知らなかった方は、この記事で知識のアップデートを一緒にしていきましょう。園の不適切保育を見てしまい、どうしたらいいかわからない先生もこの記事で不安解決しましょう。
この記事では、不適切な保育を知りたいと思っている方のお悩みを解消します!
それでは、どうぞ!

この記事はこんな人におすすめ!
- 違和感を解消したい人
- 不適切な保育を知りたい人
- 虐待と不適切保育の違いを知りたい人
- 経験の浅い管理職の方
※この記事では、不適切保育と虐待について説明していきます。

不適切保育とは
まず、「不適切保育」には定義があります。
「保育所での保育士等による子どもへ
保育所等における虐待等の防止及び 発生時の対応等に関するガイドライン|令和5年5月 こども家庭庁より引用
の関わりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に 照らし、改善を要すると判断される行為」
不適切保育の分類
では、どのような行為が不適切保育に分類されるか説明します。
- 子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり
- 物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ
- 罰を与える・乱暴なかかわり
- 一人ひとりの子どもの育ちや家庭 環境を考慮しないかかわり
- 差別的なかかわりを不適切な保育の具体的な行為類型として示している
「罰を与える・乱暴な関わり」など、虐待のイメージに近い行為も含まれています。
虐待と不適切保育は違うものですが、内容によっては虐待行為に含まれるため、未然に防止すること・改善することが必要です。
虐待とは
次に虐待についてです。虐待の定義は以下の通りです。
保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う下記のいずれかに該当する行為です。また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されてます。
保育所等における虐待等の防止及び 発生時の対応等に関するガイドライン|令和5年5月 こども家庭庁より引用
虐待の例
以下が虐待の例です。研修などでよく目にする内容だと思いますが、改めてまとめます。
- 身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 性的虐待 :保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
- ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる12又は4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
- 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
「虐待」は家庭で起きることだと世間では認識されますが、保育施設や幼稚園でも起こり得る行為です。
つまり、保育者の言動も虐待に値することがある。ということです。自分の保育や言動と次のような言葉が重なる場合は危機感を持って変えていきましょう。「強制的」「強引」「無関心」「暴力的」「性的」などが当てはまると思います。
保育園施設等が行う未然に防ぐ対応とは
これを見ている方の中には、管理職の方もいます。管理職の方は園全体で取り組むチェックリストなどが参考になると思います。現場で働いている先生は、自分を守るためにも日々の記録は欠かせません。未然に防ぐ方法があることを知っているだけで、現状を改善することができますよ。
保育施設等における虐待等の未然防止は以下の通りです。
- 各職員や施設単位で、日々の保育実践における振り返りを行うこと
- 職員一人一人がこどもの人権・人格を尊重する意識を共有すること
園全体で取り組むためには、全国保育士会の「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」を活用しましょう。私も企業の保育園に勤めていたときに、定期的に虐待に関するチェックリストが実施されていました。自身の保育を見直すきっかけとなり、初心にかえり、気が引き締まります。
一時期「あたりまえを見直す」という本が流行ったように、「自身の保育を見直す」ことは不適切保育・虐待に関わる行為を未然に防ぐことができること、園を運営するにあたって事件事故防止に繋がること、実施している記録を残すことで職員や園を守る証拠になることなど、メリットが多いと考えます。
保育者それぞれ考え方が違いますし、10人いれば10人の正義があるため、チェックリストなどを活用して、保育に対する考え方のブレを整えていくことは、事故事件防止のためにも重要だと思います。
個人ができること(手段)
- 職員間で情報共有する ※陰口・悪口にならないように注意。※疑問に思う保育があれば信頼できる先生か主任または園長に相談する。
- 市町村等に情報提供、相談を行う。 ※まずは主任・園長に相談します。もし解決しないまたは自身がそのことで悩み仕事に集中できないようであれば、最終手段として。公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)第5条には、公益通報をしたことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない と規定されています。しかし、必ずステップを踏んでから相談しましょう。
- 自身の知識を深める。まずはここ!不適切な保育の判断がとれるようになることが重要だと思います。保育者が子どもたちにするべきことは何か、虐待・不適切保育のボーダーラインを知っていると言うことは保育者として必要な感覚です。

悩んだら活用してみて
これまでにお伝えしたことは以下のサイトに掲載されています。
知識を深める・チェックリストを活用するなどに参考にされてください。
令和5年5月 こども家庭庁
全国保育士会
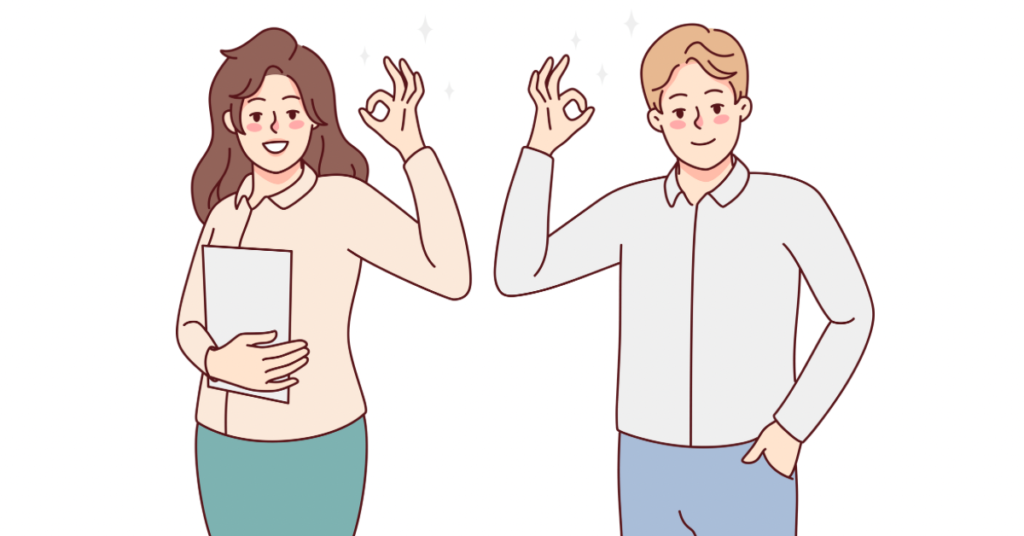
まとめ
不適切保育のまとめはこちら↓
- 不適切保育には定義があり、分類がある
- 虐待の定義や分類もある
- 保育園ができることはチェックリストを活用して、保育の価値観のズレを整えること
- 個人ができることは、上司に相談又は行政に相談ができる
日々、時間と仕事に終われ、見失っているものもあるかもしれません。経験を積んでいくと、「子どものためと思っていた行動がいつの間にか自己満に変わっていた」なんてことも起こり得ます。実際にそのように感じる同僚をたくさん見てきました。私の場合、他業種から転職したため、保育業界の仕事の仕方や考え方のギャップを感じました。短大で勉強した保育と現実に起きている保育の違いを見て「これが保育?」とショックを受けたこともありました。「これは適切な保育なのか?」と感じることに対して、「自分はそうはならないぞ」と決心しても、クラスリーダーになると時間や人間関係にも気を張らないといけなくなり、つい子どもの行動を急がせてしまうこときもあります。
皆さんもそんな経験があると思います。「このままじゃまずい」「こんな先生になりたかったわけじゃないのに」と自信をなくしたり落ち込む前に、正しい知識をつけて、保育者としての判断力を養うことが回避の策だと考えます。
1人でも多くの先生が、子どもに不適切な保育をしてしまわないように、知識を提供できたら嬉しいです。